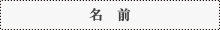 |
|
|
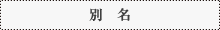 |
|
|
|
|
|
|
ねざめぐさ めざましぐさ かぜききぐさ 荻芦(おぎよし) |
|
|
|
|
|
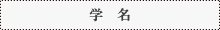 |
|
|
|
|
|
|
Miscanthus sacchariflorus |
|
|
|
|
|
|
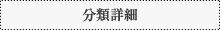 |
|
|
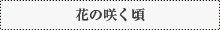 |
|
|
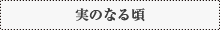 |
|
|
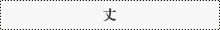 |
|
|
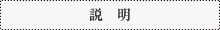 |
|
|
|
|
|
|
荻は、万葉集では3首詠われているだけで、葦49首、尾花43首に比べるととても少ないが、これは葦も尾花も全国的に分布し、ヨシズに利用されたり、茅葺屋根の材料に使われているのに対し、荻は自生地も限られていて、ヨシズの材料としても使われることが少なかったことが原因と考えられる。
和泉式部は、
霜がれは 侘びしかりけり あき風の 吹くには萩の 音づれもしき
(霜枯れはわびしいものです 秋風の吹くころは荻の葉音がして あなたの訪れもありましたのに)
ねざめねば 聞かぬなるらむ 荻風に
吹くらむものを 秋の夜ごとに
(物思いで夜中に目覚めたりなさらないから お聞きにならないのでしょうか あなたをお招きする荻風が 秋の夜ごと吹かないことがあるでしょうか)
などと、荻に関する歌をたくさん詠んでいる。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
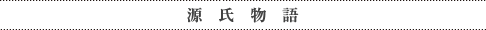 |
|
|
軒端荻(のきばのおぎ)は嫌な感じがするが、こんなふうに思い出してくださったのも嬉しくて、返歌は、早く詠んだことだけを下手な言いわけにして小君に手渡す。
ほのめかす 風につけても 下荻の なかばは霜に 結ぼほれつつ
(ほのめかされる便りをいただいても 荻の下葉が霜にあたったように わたしの気持ちは萎れて)
字は下手なのにごまかして、洒落たように書いてあるのは品がない。 |
|
|
[夕顔] |
|
|
大将は、
荻の葉に 露ふきむすぶ 秋風も 夕ぞわきて 身にはしみける
(荻の葉に露を結ばせる秋風も 夕暮には特に身に沁みます)
と書いて、
〈絵に添えて送りたい〉
と思われるが、姫宮を想っている様子がほんの少しでも漏れたら、ひどく面倒ことになる世の中だから、ほんの些細なことも、匂わすわけにはいかない。 |
|
|
[蜻蛉] |
|
|
三澤憲治訳『真訳 源氏物語』から抜粋 |
|
|
|
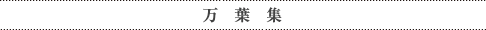 |
|
|
葦辺なる 荻の葉さやぎ 秋風の 吹き来るなへに 雁鳴き渡る
(葦辺にある 荻の葉をそよがして 秋風が吹いてくるのにあわせて 雁が鳴いて通る)
|
|
|
読人しらず(巻十―二一三四) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|