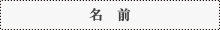 |
|
|
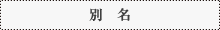 |
|
|
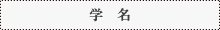 |
|
|
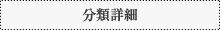 |
|
|
 |
|
|
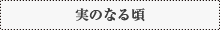 |
|
|
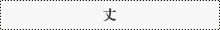 |
|
|
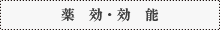 |
|
|
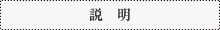 |
|
|
|
|
|
|
山栗は、柴栗(しばぐり)ともいい、古くは縄文時代から食用とされてきた山に自生していて、現在栽培されているさまざまな品種の原種となっている。
果実は栽培されているものと比べるととても小さいが、味は滋味に満ちている。
クリの名は、「くろみ(黒実)」が「くり」と呼ばれるようになったといわれる。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
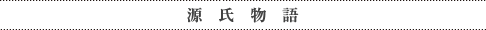 |
|
|
常陸宮の女君(末摘花)だけは、妙に礼儀正しく、なにもしないではいられない昔気質なので、
〈どうしてこの準備を他人事として聞き流すことができようか〉
と思われて、作法どおりに用意なさった。殊勝な心がけである。青鈍色(あおにびいろ)の細長を一襲(ひとかさね)、落栗色(おちぐりいろ)とか、なんとかいう昔の人がもてはやした袷(あわせ)の袴(はかま)を一揃い、紫が白っぽくなっている霰模様(あられもよう)の小袿とを、立派な衣裳箱に入れて、上包みもきちんとして贈られた。 |
|
|
[行幸] |
|
|
三澤憲治訳『真訳 源氏物語』から抜粋 |
|
|
|
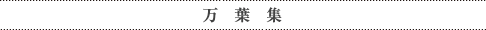 |
|
|
瓜食めば 子ども思ほゆ 栗食めば まして偲はゆ いづくより 来りしものそ まなかひに もとなかかりて 安眠しなさぬ
(瓜を食べると 子どもたちが思い出される 栗を食べると、なおさら偲ばれる どんな宿縁で生まれてきたのか 眼前に むやみにちらついて 眠らせないのは)
|
|
|
山上憶良(巻五―八〇二) |
|
|
|
|
|
三栗の 那賀に向かへ る曝井の 絶えず通はむ そこに妻もが
(三栗の 那賀の 真向かいにある 曝井のように 絶えることなく通おう そこに 恋人がいたらいいのに) |
|
|
読人しらず(巻九―一七四五) |
|
|
|
|
|
松反り しひてあれやは 三栗の 中上り来ぬ 麻呂といふ奴
(ぼけてしまったのかしら 月の半ば過ぎまで わたしのところへ来ない 麻呂とい 奴は) |
|
|
読人しらず(巻九―一七八三) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|