![�[�w�̌��i�Y�Ȃɓ��݂���^�̈Ӗ��𗝉����A��������I�ȃC���[�W�ɓ]���B�j](image/top.gif) |
 |
|
|
�[�w�̌��@�Y�Ȃɓ��݂���^�̈Ӗ��𗝉����A��������I�ȃC���[�W�ɓ]������B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�w���A���x�̉����\��
�����́q�ގ��r�Ƃ����T�O
�@ �t�[�R�[�́A�w���t�ƕ��x�ŁA�����ł́q�ގ��r�Ƃ����T�O���m���\�z��������������Ă����Ƃ����B�����̉��߂�����Â����̂��q�ގ��r�Ȃ�A�ڂɌ�������́A�ڂɌ����Ȃ����̂͂��ׂāq�ގ��r�Ƃ������_����Ƃ炦���Ă����B�u��n�͋���ʂ��A�l�̊炪���ɔ��f���A���͂��̌s�̂Ȃ��ɐl�Ԃɖ����閧���h���Ă����v�̂��B�l�Ԃ��v�������ׂ����̂́A�˂ɂȂɂ��̖͎ʂł���A����́u�l���̌���A���E�̋��v�ł������B
�@
�@�t�[�R�[�́A16���I�́q�ގ��r�ɂ�4�̎�v�Ȍ`�Ԃ�����Ƃ��Ă���B
�@�K�� �@
�@�قȂ������̂��������ɐڋ߂��A�ڐG���āq�K���r����B���E�͖����̕��ՓI�ȁq�K���r�ł���B�A���͐�����p�ɂ����ē����ƓK�����A�����͊��o��p�ɂ����Đl�ԂƓK�����A�l�Ԃ͒m���ɂ����Đ��ƓK������B
�A���� �@
�@�����͂Ȃꂽ��̂��̂��A�������ɔ��f���A���������B����͂܂�őo�q�̂悤�����A���ɂ��������̂悤�ł�����B���������������n��̐��ł���悤�ɁA���͓V��̐A�����B�l�Ԃ͓V��Ƃ��Ȃ������Ԃ�̓����ɐ����������A�������ēV��Ɏx�z����邱�ƂȂ��A���ׂĂ̊����͂��h���Ă���B�l�Ԃ̓��ʂ͓V�f����B
�B�ޔ� �@
�@�ގ��́A�����킸���ȗގ��ł��ގ��Ƃ݂Ȃ�����A�����̋߉��W�����肾���B���ƓV��Ƃ̊W�́A���Ƒ�n�Ƃ̊W�ɁA�����ƒn���̊W�ɂȂ��炦�邱�Ƃ��ł���B�������A���́q�ގ��r�������ǂ�̂͐l�Ԃł���B�l�Ԃ͐��E����Ƃ������܂��܂ȗގ����A���͂̐��E�ɂӂ����ѓ`�d����B�l�Ԃ����ގ��W�̎x�_�A���E�̒��S�ɂق��Ȃ�Ȃ��B
�C���� �@
�@�ގ��́A���E�̂��܂��܂ȕ��̉^����U�����A�����Ƃ����ꂽ���̂��߂Â���B����͕����m���������ɓ��ꉻ���A���̌ʐ������ł����邩��A�����h�����Ƃ��锽���݂����B���E�͋����Ɣ����Ƃ̂�������ύt�^���ł���B�͐��ɁA��C�͑�n�ɔ������������B�����炻���a�������邽�߂ɁA��C���Ɛ��̂������ɁA������n�Ƌ�C�̂������ɂ������B��C�͔M�����̂Ƃ��ĉƗאڂ��A��C�̎��C�͐��̎��C�ƓK������B����ɋ�C�̎��C�͉̔M�������炰�A�����悤�ɋ�C�̔M���͐��̎��C���Ȃ܂������������̂ɕς���B���̎��C�͋�C�̔M���ɂ���Ă������߂��A��n�̗₽�����������炰��B
�@
�@���̂悤��16���I�̐��E�́A�q�K���r�q�����r�q�ޔ�r���q�����Ɣ����r�ɂ���Ďx�����A�ێ������B�܂�q�����Ɣ����r�Ƃ��A���܂��܂ȕ��̎��ȓ��ꐫ���`������Ƃ������Ƃɂ���B�Ƃ͂����Ă��A���́q�ގ��r�����E�̒����Ƃ��Ď��o�����ɂ́A�����̂ɂȂɂ��̂��邵���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ɉB���ꂽ�ڂɌ����Ȃ��ގ��́A�ڂɌ�����W�����K�v�ł���B�t�[�R�[�̓��l�T���X�̓N�w�҃o���P���X�X�́u�_�͂����̕����B�����������Ƃ͂����A���ʂ̕W�������������ƂɌ����邵�邵�Ȃ��ɂ͉��ЂƂc����͂��Ȃ������v�����p���āA�ގ��̂��邵���_�̃T�C���ł��邱�Ƃ��m�F���Ă���B���Ƃ��g���J�u�g����a�Ɍ����Ƃ��ꂽ�̂́A���̐A���̎�q�������������������ɐl�Ԃ̂܂Ԃ������āA�_�́q���邵�r�i�L���j��m��������ł���B
�@
�@���̂悤��16���I�̐l�Ԃ́q�m�r�́A�ЂƂ��ɗގ��́q���邵�r����ǂ��邱�Ƃɂ������B���E�̂��ׂĂ̂��͔̂閧���h���A�u�����Ȃ����́v���u��������́v�Ƃ��ĂƂ肾�����B������16���I�́A�L���̈Ӗ�����������ߊw��A�L�����m�̂Ȃ����A���̖@�������߂�L���w��������ɂȂ�A���E�̑��e�́A�L���A��́A�����A�Í����Ђ��߂������傫�ȏ����̂悤�Ȃ��̂ƂȂ�B���R�́A�u�L���w�Ɖ��ߊw���㉺�ɏd�˂ւ��Ă�A�킸���Ȍ��݂̂Ȃ��ɂƂ炦���Ă���v�B���R���_��I�ł�������A�F���̑Ώۂł������肷��̂��A�u���̏d�Ȃ肠���̂����ɗގ��W�̂킸���Ȃ��ꂪ���邩��ɂق��Ȃ�Ȃ��v�B
�@�������������q�m�r�́A�ߏ�ł���ƂƂ��ɁA��ΓI�ȕn���Ƃ�����B�ގ��͂ЂƂ̗ގ��ɂƂǂ܂炸�A�ׂ̕��ƊW���邱�Ƃɂ���ĐV�����ގ����ɐ���ł����Ƃ����Ӗ��ł͉ߏ�ł��邪�A�˂ɓ������̂����F���ł����A�ی��̂Ȃ��������ē��B�ł��Ȃ��Ƃ���ł����F���ł��Ȃ��Ƃ�������ɒǂ�������Ƃ����Ӗ��ł́A�n���Ƃ����킯���B
�@
�@�܂��ɂ��̓_�ɂ����āA���̗L���ȏ��F���i�~�N���R�X���X�j�Ƃ����ϔO���A�\�Z���I�́q�m�r�ɂ������{�I�Ȗ�����������悤�ɂȂ�B����͓�d�����ꂽ�ގ��̂͂��炫�����R�̂�����̈�ɓK�p���A���Ԃ���f�����Ƃ��Ԃ��ۏ��Ă�����F���i�}�N���R�X���X�j�Ƃ����������B�����V���̉��I�Ȓ������A�Â���n�̐[�w�ɔ��f���Ă���ƒf������B�������̏��F���Ƒ�F���Ƃ̋����͖����ł͂Ȃ��B�v���\�ł���A���̌��ʂ��܂��܂ȑ����W�͂������ɂ������������߂������߂ɁA���S�ɕ����ꂽ�̈�ƂȂ�B�L���Ɨގ��Ƃ̂���ނ�̎��R�́A�F���̓�d�����ꂽ�`�ۂɂ��������āA�݂�������Ă��܂��̂��B
�@
�@���̂悤�ɏ��F���̊ϔO��16���I�ɂ����ċ^�����Ȃ��d�v�����A����͓����̐l�X�������M���Ă�������ł͂Ȃ��A�ގ��̖����̖L�����ƒP���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��������炾�A�ƃt�[�R�[�͎w�E����B�܂菬�F���Ƒ�F���̊W�ɁA���̒m�ɂ�������ۏƁA�m���킫�ł���E�Ƃ��v�l����Ȃ���Ȃ�Ȃ������Ƃ����킯�ł���B���̓����K�R���ɂ���āA���́q�m�r�͔����Ɩ��p��̂��̂Ƃ݂Ȃ����ƂɂȂ�B
�@
�@�\�Z���I�̔F���́A�����I�Ȓm�ƁA���p�̎g�p����h�������T�O�ƁA�Ñ�̃e�N�X�g�̍Ĕ����ɂ���Č��Ђ��܂�����A�̕����I��Y�Ƃ́A�s����ȍ����ɂ���č\������Ă����悤�Ɏv����B���̂悤�ɍl����ƁA���̎���̊w��́A�Ǝ�ȍ\�������������̂̂悤�Ɍ����A�q�Ñ�l�r�ւ̒����ƁA�����R�I�Ȃ��̂ւ̚n�D�ƁA�����ߑ�l�����Ȃ̓����ƌ��Ȃ��Ă��邠�̎���̍������ɂ������邷�łɖڂ��߂��������ӗ͂Ƃ��Βu�����A���R�ȏ�ɂ����Ȃ������Ǝv���邩������Ȃ��B�����Ă��̎O�̉ԕق������オ�A�O�����ꂽ�X�̍�i��X�̐��_�Ƃ������ɁA���f���Ă���̂��Ǝv���邩������Ȃ��������B�������ۂɂ́A�\�Z���I�̒m�͍\���̕s���ɋꂵ�킯�ł͂Ȃ��B���ɁA���̒m�̋�Ԃ��K�肷��z�u�������ɐ��k�Ȃ��̂ł��������́A���łɂ����̌����Ƃ���ł���B�����Ă܂��ɂ��̌������������A���p����є����A��e���ꂽ���e�ł͂Ȃ��v�����ꂽ�`���Ƃ��Ă̂Ƃ̊W����������̂��B���E�͉�ǂ��˂Ȃ�ʋL���ł������A�ގ��Ɨމ��W���[�����邱���̋L���́A���ꎩ�̑����W�̌`���ɂق��Ȃ�Ȃ��B����䂦�A�F�����邱�Ƃ͉��߂��邱�Ƃł���B���Ȃ킿�A�ڂɌ�����W������A����������Č���Ă�����̂ցA����Ȃ��ɂ͕��̂Ȃ��Ŗ��閳���̌��t�ɂƂǂ܂�ɂ������Ȃ����̂ւƁA�������ƂȂ̂��B�i�t�[�R�[�u���t�ƕ��v�n�ӈꖯ�E���X�ؖ���j
�@
�@�u�����v�Ɓu���p�v�̋����́A�\�Z���I�́q�����ꂽ���́r�̗D�ʐ����ے����Ă���B�܂肱�̎���́A�b����錾�t���A�q�����ꂽ���́r���d�v�ł���A���ꂱ�����^�����Ǝv���Ă������炾�B�����ł́u��������́v�Ɓu�ǂ܂����́v�Ƃ��A�u�ώ@���ꂽ���́v�Ɓu�l�ÂĂɕ��������́v�Ƃ���ʂ��ꂸ�A���̌��ʎ����ƌ��ꂪ�����Ɍ�������Ȃ߂炩�ȘA���ʂ��\�������B���Ƃ��Δ����w�҃A���h�����@���f�B�́w�ւƗ��̘b�x�ł́A�֗ވ�ʂɂ��Ă̔����w�I�Ȑ��m�ȋL�q�ƁA���ցA�_��杁A��ցA��ȂǁA�_�b�▂�p�Ɋւ��邱�Ƃ�����ɕ��ׂ���B����͂킽���������猩��A�����ȍ����Ƃ����v���Ȃ����A�A���h�����@���f�B�ɂƂ��Ắq�����ꂽ���́r�ł��鎩�R���אS�ɏn�����Ď��^�����ɂ����Ȃ��B����͂������č���ł͂Ȃ��A��ΓI�ȁq�m�r�ł��������炾�B
�@�C�̐[�݂ɂ��A�V��̍��݂ɂ��A�l�Ԃ������ł��Ȃ����̂͂ȂɂЂƂȂ��B���R�͌���ł���A����͏��������̂ł���A�͂Ă��Ȃ��s������߂̑Ώۂł������B�܂茾�ꂷ�Ȃ킿���R�ł���A���t���Ȃ킿���ł������L���ʼn��I�Ȏ���A���ꂪ16���I�������̂��B�����A���́q���R�Ƃ��Ă̌���r�Ƃ������݂̋L���́A�킽�������́q�m�r�̂Ȃ��ɂ͂ȂɂЂƂc���Ă��Ȃ��A����͂����u���w�v�Ɍ���������邾�����A�ƃt�[�R�[�͂����B
�@�\�㐢�I�S�ʂɂ킽���āA����ɂ͍����̂����ɂ�����܂ŁA���Ȃ킿�A�w���_�[���[������}�������A�A���g�i���E�A���g�[�ɂ�����܂ŁA���w�����̎������ɂ����Ď��݂��A���̂��������̌��ꂩ��ӂ����f��������Đ藣����Ă���̂́A���ꂪ���́u���������v���`�����A�������邱�Ƃɂ���āA����̕\�ۓI�@�\�@���邢�͋L�����Ȃ��@�\����A�\�Z���I�ȗ��Y����Ă������̐��̂܂܂̑��݂ւƂ����̂ڂ�������ɂق��Ȃ�Ȃ��B�i�t�[�R�[�u���t�ƕ��v�n�ӈꖯ�E���X�ؖ���j
�@
�@�q���̂܂܂̑��݁r�Ɏ䂩���̂́A�t�[�R�[�����������w�҂����ł͂Ȃ��B�킽�����V�F�C�N�X�s�A�㉉�ɋ�藧�Ă�̂́A���������q���R�Ƃ��Ă̌���r�֑k�s���悤�Ƃ��閳�ӎ��̗~�������邩�炩������Ȃ��B
|
|
|
|
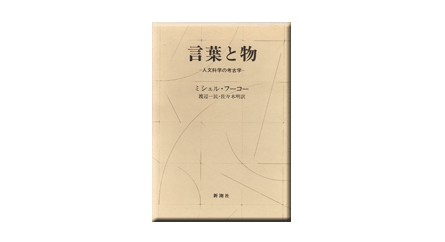 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|