 |
 |
|
|
深層の劇 戯曲に内在する真の意味を理解し、それを飛躍的なイメージに転化する。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
シェイクスピアを読む
シェイクスピアは言語の劇
演劇と映画とはちがう。どこがちがうかといえば、つぎのような演劇成立過程の図を見れば一目瞭然である。
1 具体的な事物(現実課程)
↓
2 概念的な意味と像把握(人間の内部過程)
↓
3 文字による意味と像表現(戯曲・台本過程)
↓
4 言語と補助手段による意味と像表現
(演劇表現過程)
このように演劇は、台本の文字によって表現された意味と像とを、俳優が言語に転化させる芸術である。ところが映画は、1、2、3までの過程は同じだが、4がちがう。映画では、言語ではなく、「映像による意味と像表現」になるのである。つまり映画は、シナリオの文字によって表現された意味と像とを、映像に転換させるところに本質がある。
たとえば言語表現では、「犬」という言葉は、特定の犬だけをさすのではなく、黒い犬も、白い犬も、大きな犬も、小さな犬も、犬という言葉に含むことができる。しかし映像表現では、映像で映し出された「犬」は、その具体的な犬以外のなにものでもない。このように具体的な犬の映像と「犬」という概念とが一義的にむすびつくことが、映像表現の特長である。これは、「犬」のような具体的な対象ではなく、精神状態の場合にもまったく同様だ。たとえば、「悲しい」という言語表現が、映画表現では、かならず特定の情景や事件の映像に一義的にむすびつけられる。言語表現としての「悲しい」という言葉は、本来、かならずしもある特定の条件とむすびつくものではない。友人と死別しても、恋人と喧嘩しても、子どもが病気でも「悲しい」という言葉で表現することができる。しかし、映像表現では、「悲しい」という概念は、かならず特定の情景または事件とむすびつくのである。
シェイクスピア作品には優れたものが多いので、現在でもしばしば映画化されるが、ほとんどが成功していないのは、この演劇表現と映画表現との差異を理解していないからである。
演劇表現と映画表現との差異は、つまるところ、映画は言語を無化していくのに対し、演劇は映像を無化していくことを意味する。だからシェイクスピア劇を映画化する場合、「シェイクスピアの言語は最後にはなくなってしまうぞ」というくらいの覚悟がいるのに、これまでの映画化はそんなことはまったく考慮せず、原作の言語をそのまま踏襲して俳優にとうとうと喋らせる。しかも、ケネス・ブラナーのように自己肯定の臭い演技で。これではシェイクスピアを映画化したことにはならないのである。
シェイクスピアを映画化するなら、シェイクスピアの物語的な意味を映像的な無意味に転換する場合、また物語的な無意味を映像的な意味に転換する場合、映画でしかつくれない〈まったく新しいシェイクスピアの映像〉を作り出すしかない。これまでの映画化でそれができているのは、ジャン・リュック・ゴダールの1987年作品『ゴダールのリア王』だけだといっていい。
前述したように、演劇は、文字によって書かれた意味と像とを、俳優が言語に転化させる芸術であり、照明や音楽や大道具や小道具や衣裳は、あくまでも言語を助ける補助手段にしかすぎない。だから演劇の生命とか価値とかは、観客の度肝を抜く舞台装置や音響や絢爛豪華な衣裳にあるのではなく、まさに俳優が語る言語のなかに、現在と歴史とが生々しく生きているかどうかによってきまる。つまり俳優が、みずからのなかに現実性と歴史性を保持しえないかぎり、けっして優れた演劇作品にはならないのだ。
この演劇の特性をもっとも知り尽くしていたのが、シェイクスピアといえる。シェイクスピアは音楽好きだったから、たくさんの音楽を使ったが、本質的には言語だけを頼りにして、あの豊饒で、深遠な幻想世界を描き上げたのである。このように、シェイクスピア劇が〈言語〉の劇であることを如実に示し、演劇史上に燦然と輝くシーンを、『十二夜』から抜き出してみる。男装したヴァイオラがシザーリオと名を変え、密かに愛する公爵に、じぶんの姉という架空の人物(実は自分自身)に託して愛を語るところだ。
公爵 シザーリオ、もう一度、あの人のところへ行け! 財産も領地もいらない。おれが惹かれるのはオリヴィアその人だと言ってくれ!
ヴァイオラ(シザーリオ) 愛せないと言われたら?
公爵 聞きたくない。
ヴァイオラ でも聞かなくては・・・もしある女が、あなたを愛し、苦しんでるのに、愛せないと言われたら?
公爵 こんな苦しい恋に耐えられる女なんかいるものか!女の愛はちっぽけなもの。おれの愛は海のように凄まじい。つまらん女の愛とは比較にならん。
ヴァイオラ でも知っています、わたしは。痛いほど。
公爵 なにをだ?
ヴァイオラ 女の愛がどんなものか!けっしてわたしたち男に劣りません・・・父の娘が、ある男を愛しました。わたしが女なら、あなたを愛したような、深い愛でした。
公爵 ・・・で、どうなった?
ヴァイオラ 白紙のままです。だれにも恋を打ち明けないで、バラのつぼみに巣くう虫が、花の命をむしばんでゆくような片想いに・・・ひとり悩んだのです。 そして、しだいにやつれてゆき・・・蒼ざめた憂いに沈み・・・それでも、石の像のように辛抱強く、悲しみに耐えていました・・・これがほんとうの恋ではありませんか? わたしたち男はやたらと誓いを立てます。でもそれは、見せかけだけのもの。心にもないことばかりで、愛ではありません。
公爵 (心打たれて)で、その娘は恋に死んだのか?
ヴァイオラ ・・・今はわたし一人です・・・わたし一人しかいないのです。
このヴァイオラの言葉は、哀切で美しい。だがここで注目すべきは、この言葉の特異な演劇的効果だ。 ここでヴァイオラは、単に公爵に伝わるはずのない愛を告白しているだけではない。実際に舞台に立ちつくしている彼女自身の姿を、じぶんの言語によって形象化しているのである。言いかえるなら、言語のつむぎ出す想像上のイメージが、そのままヴァイオラの姿に投影され、彼女自身がそのタブロー(静止画)となっている。つまり、今舞台に立っているヴァイオラは、そのまま虫に食い荒らされているバラであり、悲しみに耐えている「忍耐の像(石像)」そのものなのである。
このように、シェイクスピア劇は言葉の随所にメタファーが隠されている、とても意味深い〈言語〉の劇だ。〈言語〉によって無限の意味と像を表現したいのなら、それは演劇でしか達成されないのである。 |
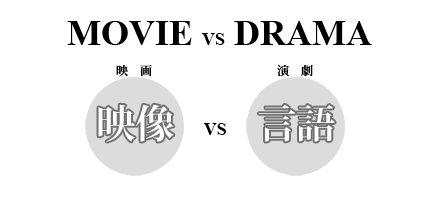 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|