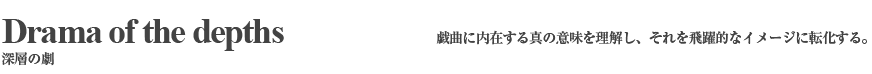 |
 |
|
|
深層の劇 戯曲に内在する真の意味を理解し、それを飛躍的なイメージに転化する。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
演劇の師
吉本隆明氏との出会い
人間はある時、その人の一生を決める〈心の師〉と出会う。
わたしの場合は、桐朋学園演劇科の学生のときだった。
当時桐朋学園では、土曜講座というのがあり、芸術各方面の著名人を招いて芸談や学識を聞いていた。
昭和45年、風薫る5月の土曜日、その人はやってきた。
飾らない風貌ではあるが、その目は鋭く、輝いていた。その人は難しい話をしてもわたしたち俳優の卵には伝わらないと思ったのか、平易な語りかけではじめた。
「今日は言葉の美ということ、つまり言葉の表現が、なぜ美を成立させるのかという、たいへん基礎的な問題についてお話ししたいとおもいます」。
なんどもなんども念を押すような話し方に特徴があった。文学座の『女の一生』をあげて
「若い女優が演じるほうが創造力で補って演じることができるのでやりやすい、婆さんのばあいは多少なりとも自己体験があるのでそれに制約されてしまう」
で共感し、
「言語表現が美を成立させている要素に〈韻律〉〈選択〉〈転換〉〈喩〉がある」
ですっかり魅了されてしまった。
この人こそ戦後日本が生んだ世界に通用する最大の思想家、吉本隆明氏であった。
土曜講座が終わると、わたしは新宿の紀伊国屋に走った。書棚を見た。
『言語にとって美とはなにか』第Ⅲ部劇、第Ⅰ篇成立論。
それは目のさめるような鮮やかな演劇の定義づけだった。
それ以来、氏の著作が出版されるたびに読みつづけて三十数年。それ以来、氏と会ったことも、話したこともないが、わたしが演劇を創造するときの師はいつも吉本隆明氏だった。
この演劇サイトで展開する演劇論はすべて、この心の師から教わったものである。換骨奪胎したものではなく、ほんものに接したいという方は、ぜひ吉本隆明氏の著作にあたってみられることをお勧めする。特に、『言語にとって美とはなにか』は、演劇を目指す人の必携の書だし、『アフリカ的段階について』は、未来を思考する上での指針となる名著である。
|
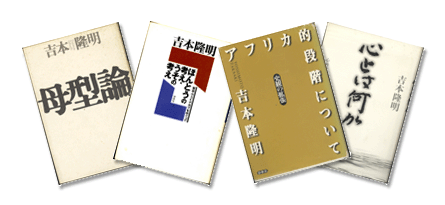 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|