 |
 |
|
|
深層の劇 戯曲に内在する真の意味を理解し、それを飛躍的なイメージに転化する。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
シェイクスピアを読む
観客の心を饒舌にする台詞
シェイクスピアの言葉は、いろいろな趣向が凝らされていて、実に多彩で豊かだ。それを挙げてみると、
①劇の幕開きに合致した言葉
②人生の実相を鋭く切り取る言葉
③美しく華やかな詩的な言葉
④哲学を感じさせる形而上的な言葉
⑤相手の言葉を一瞬に切りかえす言葉
⑥掛け言葉や駄洒落などの猥雑な言葉
これらの言葉はドラマの中でバランスよく保たれ、美しく謳いあげるときは限りなく美しく、下卑るときは徹底的に下卑るように、言葉の振幅の幅が大きいのがシェイクスピアの特質といえる。
だがこのシェイクスピアの言葉は、裏を返せば、飾り気の多い、わざとらしい言葉ということにもなる。ロシヤの文豪トルストイは痛烈な批判をしている。
どんなものでもシェイクスピア劇を読みはじめると、私にすぐさまじゅうぶん明白に確信できるのは、シェイクスピアには性格描写上の唯一とは言わぬまでも大事な手段である―「言葉」というものが欠けていること、つまり、一人一人の人物が自分の性格にそなわった言葉で話すような、そういう言葉が欠けている、ということだった。シェイクスピアにはそれがないのである。シェイクスピアの人物たちはいずれも自分の言葉ではなくして、つねに同一のシェイクスピア流の、虚飾たっぷりな、不自然な言葉で話すが、それは描かれている登場人物がそれで話せないのみか、いつ、いかなる所においても、いかなる生きた人間も話すはずのない言葉なのである。(トルストイ「シェイクスピア論および演劇論」中村融訳)
小説家トルストイらしい批判だが、かれが言うように、言葉が登場人物の性格に反映されていないのは確かだが、その欠点を補ってあまりある魅力がシェイクスピアの言葉にはある。
たとえば、『ハムレット』でのオフィーリアの狂乱のダブルイメージの言葉もそうだが、『リア王』でリア王が嵐の場面で「風よ吹け!おまえの頬が破れるまで吹きまくれ!」と、自然を擬人化して叫ぶ言葉は、未開の神人同性に起源をもち、自然との距離を救済としてみてしまう古代人の習性を表現しているように、シェイクスピアの言葉には現在のわたしたちが知るべき豊かな意味が隠されている。トルストイの批判は、「虚飾たっぷりな、不自然な言葉」を削除し、登場人物の「自分の性格にそなわった言葉」に書き直せば解決できるのだ。
それでは、喜志哲雄の『十二夜』の訳を例にして、この作業をしてみることにする。男装したヴァイオラが公爵に仕え、その公爵から大いに気に入られ、公爵が愛しているオリヴィアのもとへ恋の使者としてつかわされることになるが、実はヴァイオラは公爵を愛していることがあかされる場面だ。
ヴァレンタインと男装のヴァイオラ、登場。
ヴァレンタイン そなたへの公爵のご寵愛、このまま 続くなら、セザーリオー、そなたの出世は確かだ、何しろお仕えして僅か三日というのに、はや、そなたは大のお気に入りなのだからな。
ヴァイオラ ご寵愛が続くならなどととり立てて言われるのは、公爵のお心変り、あるいは私の御奉公の至らなさを恐れておられるのでしょうか。公爵は移り気なお方だとでも?
ヴァレンタイン いや、そのようなことは断じて。
公爵、キューリオー、従者たち、登場。
ヴァイオラ それで安心しました。おや、公爵がお見えに。
公爵 誰か、セザーリオーを見かけた者は?
ヴァイオラ こちらにおります。
公爵 そなたらはしばらくあちらに控えておれ。セザーリオー、お前はすべてを知ったのだ。私はお前に心の秘密を記した書物まで開いてみせた。この上は、よいか、あの姫君のもとへ伺い、目通りをすること、戸口に立って、踏みすえた足から寝が生える時が来ても必ずお目にかかると、侍者どもに言うのだ。
ヴァイオラ いいえ、公爵様、もしも姫君が噂通り、悲しみに沈んでおいでなら、とてもお目通りなどは。
公爵 声を張り上げ、礼儀をかまわぬもよい、むざむざ戻って来るよりはましだ。
ヴァイオラ もしもお目通りが叶いましたら、その時は?
公爵 ああ、その時こそ、私の激しい愛情をあかし、 私の一途な思いを語って姫の心をゆさぶるのだ。こうして私の悩みを伝える役、お前にはまことにふさわしい。若いお前のこと、もっといかめしい顔つきの使者と違って、よく聞き入って貰えよう。
ヴァイオラ いいえ、そうは思いませんが。
公爵 いや、間違いない。何しろ、お前を一人前の男扱いする者は、お前の若さが分からぬやつなのだからな。お前の唇は、ダイアナの唇よりもなめらかでルビーのようだし、お前の細い声は、乙女さながらに鋭いし、そう、お前は、どこからどこまでも女を思わせる。お前こそ、この仕事にふさわしい役まわりなのだ。誰か四、五人、この者について行け、いや、そなたらすべてでもよい。今の私は、そばに人がいないほど嬉しい。首尾よくやることだ。その上は、お前も主人同様、主人の財産をわが財産として、気ままに暮させてやろう。
ヴァイオラ 精一杯、姫君に言い寄って参ります。だがこれこそいとわしいつとめ、誰に言い寄るにせよ、奥方になりたいのはこの私なのだ。
一同、退場する。
(喜志哲雄「劇場のシェイクスピア」)
最初のヴァレンタインの台詞で気になるのは「そなた」という言い方だ。原文ではYouとなっているのに、なぜ訳者は「あなた」でも「おまえ」でも「きみ」でもなく、「そなた」という呼び方を選んだのだろうか?それは、この物語が現代の話ではなく昔の話だという時代性を出したいからであり、ヴァイオラは実は女性だけど同僚の男性からすっかり男性だと思われていることをまずはじめに示しておきたいからだ。この場ではじめてヴァイオラが男装して登場するので、訳者の理屈としてはその通りだが、舞台の台詞としては、この短い台詞に三回も「そなた」を使うのは面白くない。つぎのようにカットしても意味は充分つながる。「公爵のご寵愛がこのまま続くなら、セザーリオー、そなたの出世は確かだ、何しろお仕えして僅か三日というのに大のお気に入りなのだからな」。
これで「そなた」という言い方は1回だけになり、少しだけわかりやすくなった。だがこの台詞回しではまだ話し言葉としてこなれていない。もちろんヴァレンタインの言っている内容はこれで充分わかるが、かれがこういうことを言うのは、ヴァイオラがわずか3日で公爵の寵愛を受けたという驚きがあるからで、この驚きをなんとか台詞にしたいものだ。つぎのようにした。
ヴァレンタイン シザーリオ、ここのままいけばキミの出世は間違いなし。たった3日でもう公爵の一番のお気に入りなんだから。
台詞を短くしたのは、訳の論理的ではあるが時代がかった台詞まわしを簡潔にして、現在の観客に通じる生きた言葉にしたいのと、個々の台詞の速度を速くして劇全体の時間を現在の観客の観劇時間に耐えうる2時間以内におさめたいからだ。「そなた」を「キミ」にかえたのは、「そなた」では日本の時代劇を連想してしまうし、時代性はほかの台詞で補い、この台詞はあくまでも現在の臨場感をだしたいからだ。ヴァレンタインの驚きは、「間違いなし」「たった」「もう」で表わすことにした。
つぎは、このヴァレンタインの台詞からヴァイオラが恋してる公爵のことを気にするところだ。
ヴァイオラ ご寵愛が続くならなどととり立てて言われるのは、公爵のお心変り、あるいは私の御奉公の至らなさを恐れておられるのでしょうか。公爵は移り気なお方だとでも?
ヴァレンタイン いや、そのようなことは断じて。
公爵、キューリオー、従者たち、登場。
ヴァイオラ それで安心しました。おや、公爵がお見えに。
ここの要は、公爵を恋するヴァイオラがヴァレンタインの言ったことに不安を感じ、「公爵は移り気なお方だとでも?」と聞くと、ヴァレンタインがそれを即座に否定するので安心するという点だ。この台詞で、ヴァイオラは公爵に会った途端に恋したことがわかる。つまり、ヴァイオラは男装して登場するが、内心は公爵に惚れている女だという二重の意味をシェイクスピアはこの短い台詞で端的に表現している。だからここの台詞は、そういうヴァイオラの恋心を観客がすぐにわかるように表現する必要がある。恋心を表わしている言葉は、「公爵のお心変り」「公爵は移り気なお方だとでも?」「それで安心しました」の三つだ。つぎのように変えた。
ヴァイオラ このままいけば、なんて言われるのは、公爵の気が変わるのを、それともぼくの失敗を心配して?・・・公爵は浮気っぽい性格ですか?
ヴァレンタイン そんなことはない。
ヴァイオラ そうですか・・・・・・(恋心から) 安心した。
ヴァレンタイン ええっ?
ヴァイオラ (慌てて打ち消す) いいえ、なんでも ありません。
観客にわかりやすくするために、創作の台詞もつけ加えた。
最後は、公爵とヴァイオラ二人きりの、この場面のもっとも緊張した重要な個所だ。ここで表現しなければならないのは、公爵のオリヴィアへの熱烈な恋心と、恋する公爵から恋の使いを頼まれたヴァイオラのやるせない恋心だ。シェイクスピアは、この公爵の恋心とヴァイオラの恋心とはまったく等価であり、絶対的な愛として描いている。この二人の燃える恋の想いをどういう言葉にしたら、それが伝わるのか? わたしには訳文では公爵もヴァイオラも演説しているようで、とても恋してるようには思えない。恋に理屈はないのだから、公爵は燃える想いを洪水のように吐き出せばいいし、ヴァイオラもそのやるせない恋心を吐き出せばいいのだ。
公爵 シザーリオはいないか?
ヴァイオラ ここにいます。
公爵 ほかのものはさがれ。
(キューリオと従者たちは去る)
公爵 シザーリオ、おまえにだけはすべて話した。あの人のところへ行ってくれ。
ヴァイオラ でも公爵、深い悲しみに沈んでおられるなら、会ってもらえないのでは?
公爵 礼儀なんか無視して騒ぎ立てろ! 会えるまでは絶対に帰らないと言え!
ヴァイオラ ・・・会えたら、何と?
公爵 この燃える想いを伝えてくれ。初々しいおまえの言葉なら、あの人も心を開く。
ヴァイオラ そううまくいくかどうか・・・
公爵 うまくいく。おまえのその、つややかでルビーのような赤い唇は女神ダイアナもおよばない。その細い声は、少女のように高く澄みきっている。いや、まるで少女と言ってもいいくらいだ。シザーリオ、星のめぐり合わせだ。おまえは、この役目にぴつたりに生まれついたのだ。4、5人、供を連れて行け。うまくいけば、おれの財産はおまえのもの。おれと同じように自由に暮らせるぞ。
ヴァイオラ 精一杯口説いてみます。(公爵は去る。 傍白)ああ、辛い勤め。公爵の妻になりたいのは、このわたしなのに・・・・・・
このように、わたしたちがシェイクスピア劇を上演するときの言葉は、喜志哲雄の訳文や市販されている翻訳の言葉とはちがう。いうまでもなく、シェイクスピアの言葉は英語で書かれている。しかも16世紀の韻を踏んだ、現在のイギリス人にもわからないところがたくさんある古い英語で書かれている。これを忠実に訳すのは翻訳者のつとめで、とても意義のある仕事だが、それを忠実に上演するのは現場の演劇人のつとめではない。わたしたちは、シェイクスピアの言葉を現在の観客に生きた言葉としてストレートに伝える必要がある。なぜなら言葉というものは、時がたてば必ず死語になるし、死語の言葉をいくらしゃべっても現在の観客は疎遠な思いをするだけで、心にはけっして響かないからだ。また言葉を現在使っているわかりやすい話し言葉にしても、シェイクスピアの歴史性と思想は絶対に伝えられるからだ。演劇はいつの時代も同時代的なものであり、一回性で終わってしまうものである。演劇は文学とちがって歴史に耐えることはできない。シェイクスピアがハムレットに言わせているように記録としては残るが、表現形式は時代の波によって、あっという間に変貌してしまう。『12th
Night』のヴァイオラの台詞をもじっていえば、悲しいことに演劇は、花の盛りが散ってゆく時なのだ。わたしがシェイクスピア上演の台本づくりで心がけるのは、
① ヨーロッパの生活様式にならって、敬語は極力使わない。
② 観客を飽きさせないように、難解な言葉や言いまわし、死語は使わない。
③ 現代の観客の心にストレートに届く、わかりやすい話し言葉にする。
④ わかりやすくはするが、シェイクスピア特有の形而上学的な物言い、歴史性、思想は尊重する。
⑤ 16世紀後半から17世紀初頭にかけての観客と現在の観客とは観劇意識が違う。台詞を饒舌にするのではなく、観客の心を饒舌にする。
ということである。
|
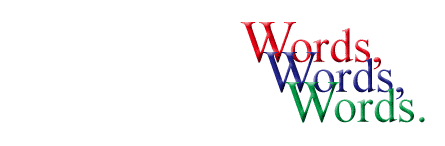 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|