 |
 |
|
|
深層の劇 戯曲に内在する真の意味を理解し、それを飛躍的なイメージに転化する。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
シェイクスピアを読む
シェイクスピアの物語とは?
シェイクスピアは、生涯37本の戯曲を書いたと言われている。真偽のほどは定かではないが、一応ここでは37作すべてシェイクスピアが書いたものとしておく。
シェイクスピアを読むと、すべて豊饒な感性によって巧みに作られているので、それぞれちがう印象を受けるのだが、おおまかにいって、三つのパターンで書いていることに気づく。
ひとつ目のパターンは、『間違いの喜劇』『真夏の夜の夢』『十二夜』などの喜劇で見られる。
たとえば『十二夜』では、双子の兄(セバスチャン)と妹(ウァイオラ)が船旅の途中で嵐に遭い、船が難破して離れ離れになる。
運良く助かった妹(ウァイオラ)は、シザーリオという男に変装して公爵に仕える。公爵は伯爵家の令嬢オリヴィアに求婚しているが、色よい返事をもらえない。そこでヴァイオラが公爵の使いとしてオリヴィアに会いに行くと、オリヴィアはシザーリオを好きになってしう。ヴァイオラにとっては迷惑な話だが、まさか女だとも打ち明けられない。ヴァイオラも公爵を愛しているだけに心は複雑である。
三人がそれぞれの片想いに悩んでところへ、死んだはずの兄(セバスチャン)が現れる。どこから見てもヴァイオラが扮するシザーリオにそっくりである。オリヴィアはこの兄をシザーリオと勘違いして求婚する。兄はオリヴィアに魅せられて結婚する。
それとは知らずに公爵がオリヴィアに求婚しに来る。オリヴィアは公爵の求婚を断り、すでにシザーリオと結婚したことを伝える。公爵は振られた腹いせから、おつきのシザーリオを絶対にオリヴィアには渡さないという。シザーリオも結婚なんかしていないといい、公爵への忠誠を誓う。オリヴィアは騙されたと怒るが、そこへ当の兄が現れる。はじめは不思議がっていた兄と妹もお互いを認めて涙の再会をする。そして、すべての誤解が解けて、公爵はヴァイオラと、オリヴィアはセバスチャンとめでたく結ばれる。
これは神話や民話などでよく見かける〈とりかえばや物語〉というパターンである。とりかえばや物語というのは、『十二夜』のように、男と女がとり替わったり、身分の高い者と低い者がとり替わったりすることによって騒動が巻き起こり、誤解したり、悩んだり、苦しんだりしながらも、それをくぐり抜けて、最後にはひとつの秩序に統一されるという物語である。
ふたつ目のパターンは、『ハムレット』『オセロー』『マクベス』『リア王』などの悲劇で見られる。
たとえば『リア王』では、古代ブリテンのリア王が退位にあたり、娘たち三人に領土を分けるとき、三人のうちでだれがいちばんじぶんを愛しているか知りたくなる。姉娘のゴネリルとリーガンは心とは裏腹に言葉巧みに愛しているというが、末娘のコーディーリアは親として尊重しているだけだという。この末娘のそっけない返事にリア王は怒り、じぶんの領土を姉娘二人に譲り、末娘を勘当してしまう。
以後リア王は、姉娘二人の邸に順繰りに暮らすことになるが、二人に冷たくあしらわれ、ついに荒野に飛び出し、乞食のように落ちぶれて放浪する。
この放浪生活の中で、リア王ははじめてじぶんに気づき、じぶんの無知を知る。コーディーリアは父の不幸を知ってフランス軍を率いてきて助けるが、再会の喜びもつかの間、ブリテン軍との戦争に敗れて処刑される。そして、最愛のわが子を亡くしたリア王は、悲嘆のあまり死ぬ。
これも神話や民話などでよく見かける〈貴種流離譚〉というパターンである。貴種流離譚とは、身分の高い人が苦労して諸国を巡り歩き、ひねくれたり落ちぶれたりしながら、最後には救済される(リア王のように救済されないで死ぬ場合もあるが)物語である。
なぜ物語がこういうパターンになるかというと、人間の精神構造や精神の働き方のパターンが、いつでもこのようになるからだ。人間はだれでも、ある困難なことにぶつかったり、精神的に追いつめられたりすると、はじめは逃げようとする。すると、そのことがどんどん押し迫ってきて、ますます追いつめられてしまう。そして、もう絶体絶命というとき、ふっと道が開けてくることがある。また、道が開けないでそこでつぶれてしまうことがある。これは人間ならだれでもそうであって、だれでも精神の働き方は、いつでもそのように作用する。だから、これが人間が書く物語のひとつの基本的なパターンになるわけである。シェイクスピアもそれに従ったのである。
三つ目のパターンは、『ペリクリーズ』『シンベリン』『冬物語』などのロマンス劇で見られる。
たとえば、『ペリクリーズ』では、アンタイオカス王は娘と近親相姦を犯している。しかし、罪に汚れた娘とも知らずに、美貌にひかれて王侯貴族たちが求婚にやってくる。王は娘をいつまでもじぶんのものにしておきたいので、求婚者たちに謎賭けをして、解けない者は容赦なく命を奪っている。ところが、ツロの領主ペリクリーズはその謎を解いてしまう。それは近親相姦を暗示していたので、ペリクリーズは身の危険を感じて故郷に逃げ帰る。
だがペリクリーズがツロにいては、王が刺客をつかわして命を奪うどころか、ツロの人民をも滅ぼしかねないので外国に逃げることにする。
旅の途中、嵐に会い、ペリクリーズだけが奇跡的に助かる。そして、たどり着いた国で槍試合をして優勝し、領主の娘セーザと結婚する。
二人が新婚生活をはじめてすぐに、「天罰が下って近親相姦の王と娘は死んだ」という手紙が届く。ペリクリーズはさっそく故郷に帰ることになるが、またもや旅の途中で嵐が襲いかかる。セーザは船中で産気づき女の子を産むが死んでしまう。ペリクリーズは悲嘆にくれるが、セーザの死体を海に流さないかぎり嵐はおさまらないといわれ、それにしたがう。
どうにかタルソという町に着いたものの、赤ん坊には長旅は無理なので、太守夫妻に養育を頼んでじぶんだけ故郷に帰る。
一方、セーザの棺はエペソスに流れ着く。医学に詳しいセリモンが薬を与えると、セーザは奇跡的に蘇える。だが、夫に二度と会えないと絶望したセーザは、尼となって神に仕える。
それから14年の歳月が流れる。ツロの国は安泰で、ペリクリーズは娘と再会するためにタルソに向かう。娘のマリーナは太守夫妻に育てられ、美しく成長するが、その美貌と才知を妬んだ太守夫人は殺害をたくらむ。マリーナは間一髪で助かるが、海賊にさらわれ、ミティリーニの女郎屋に売り飛ばされてしまう。
タルソに着いたペリクリーズは、太守から娘が死んだと聞かされ悲嘆にくれる。
マリーナは持ち前の清純さで女郎屋を抜け出し、上流階級の子女たちに、歌や踊り、針仕事を教えて暮らす。
絶望したペリクリーズは、停泊している船でだれとも口を聞かないでいる。マリーナの客だったミティリーニの太守はそんなペリクリーズを不憫に思って、マリーナなら彼を救えるのではないかと思って彼女を連れてくる。ペリクリーズははじめはかたくなに口を閉ざしていたが、マリーナの美しい声に耳を傾け始める。そして、身の上話を聞くうちに、マリーナがじぶんの娘であることを確信する。涙ながらに再会を喜び合う親子。すると、女神ダイアナが現れ、神殿に行けと告げる。二人が行ってみると、そこには死んだはずのセーザがいて、万事めでたしとなる。
このように『ペリクリーズ』は人生流転の波瀾万丈の物語である。これは次のように幸と不幸とがこれでもかこれでもかと繰り返される物語でもある。
●主人公ペリクリーズが謎を解く―幸
●その謎を解いたために故郷を追われる―不幸
●船での逃亡中、嵐に襲われる―不幸
●だが、一人だけ助かる―幸
●見知らぬ土地で槍試合に勝ち妻を得る―幸
●近親相姦の王と娘が死んだ―幸
●船旅の途中、またもや嵐に襲われる―不幸
●妻が娘を無事出産する―幸
●だが、妻は死んでしまう―不幸
●ところが、妻は奇跡的に蘇える―幸
●娘は美しく成長する―幸
●その美しさを妬んで育ての親が殺害を企む―不幸
●娘は女郎屋に売り飛ばされる―不幸
●娘の死を知る―不幸
●娘は女郎屋から抜け出す―幸
●絶望の主人公は生きる気力がない―不幸
●娘と再会する―幸
●妻とも再会する―幸
これからわかることは、幸と不幸はいつもある極端を意味しているということだ。幸は喜びの絶頂であり、不幸は悲惨のどん底である。
なぜシェイクスピアは、こんな幸と不幸とが何度も反復される、おおげさな芝居を書いたのだろうか?そんな疑問が生じたらこの幸を生に、不幸を死に変えてみるといい。そうすれば、この物語が生と死の転換のヴァリエーションにほかならないことがわかる。つまり、生がいろいろな波瀾に出会って死に瀕した体験をした後に、輝かしい再生に到達する。これが三つ目のロマンス劇のパターンである。
この三つ目のパターンは、グリム童話のそれとよく似ている。グリム童話も主人公は死に瀕するような困難にぶつかっても、けっして死ぬことはないし、たとえ死においやられても奇跡的に蘇える。『ヘンゼルとグレーテル』 がそうだし、『兄と妹』『白雪姫』もそうだ。
こどもがグリム童話のような波瀾の筋書きを面白がるのは、幼稚だからではない。子どもには、この波瀾が最後には終わり、死は必ず生に逆転することを無意識に感じているから喜ぶのだ。だから子どもには、波瀾は大げさで起伏の激しいほどいいし、主人公が死んでしまうようなことがあってはならないのだ。
シェイクスピアは、史劇で演劇の修練を積み、〈とりかえばや物語〉というパターンで喜劇を書き、さらに人間の内奥に迫りたいと〈貴種流離譚〉〉というパターンで悲劇を書いたと思えるが、こうした演劇的な研鑚の末に最後にたどり着いたのが〈生と死の逆転のドラマ〉だった。
おそらく41歳のときに書いたといわれる『リア王』と、44歳のときに書いたといわれるロマンス劇『ペリクリーズ』を比べたら、前者のほうが作品の価値は高いかもしれない。だがわたしには、ロマンス劇のほうがグリム童話と同じような〈子どもの無意識〉を含んでいるぶんだけ、読後に爽やかな印象をうける。
たとえば『ペリクリーズ』の終わり近く、娘のマリーナがたずねてきて歌を歌う場面があるが、その歌は妻を失い、娘をも亡くした主人公ペリクリーズの空虚な心に染み込んでくる抒情の歌である。その歌を聴いて、主人公ばかりか主人公と波瀾を体験した観客も慰められ、観客は生きることに欠かせないメロディを手に入れる。そしてこのメロディこそが、死を見つめた晩年のシェイクスピアが、じぶんの演劇人生を振り返って、波瀾の反復ととらえたときに得たものにちがいないだろう。 |
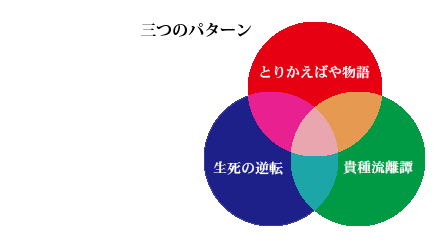 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|