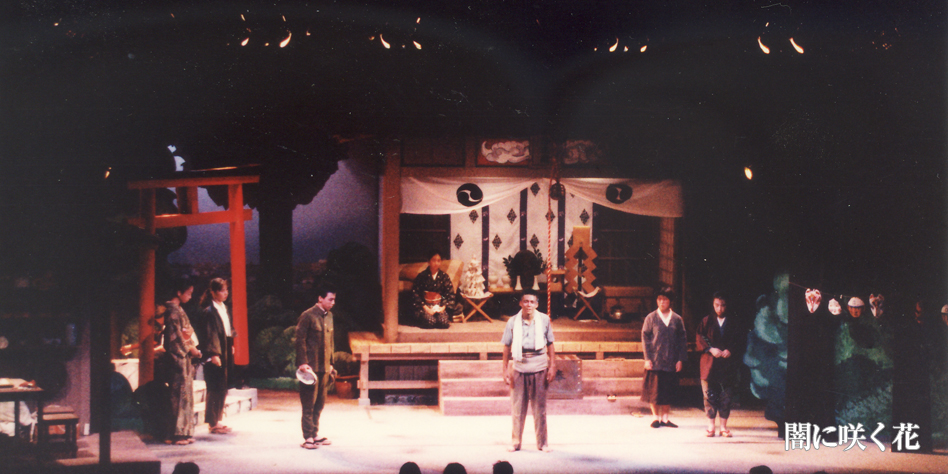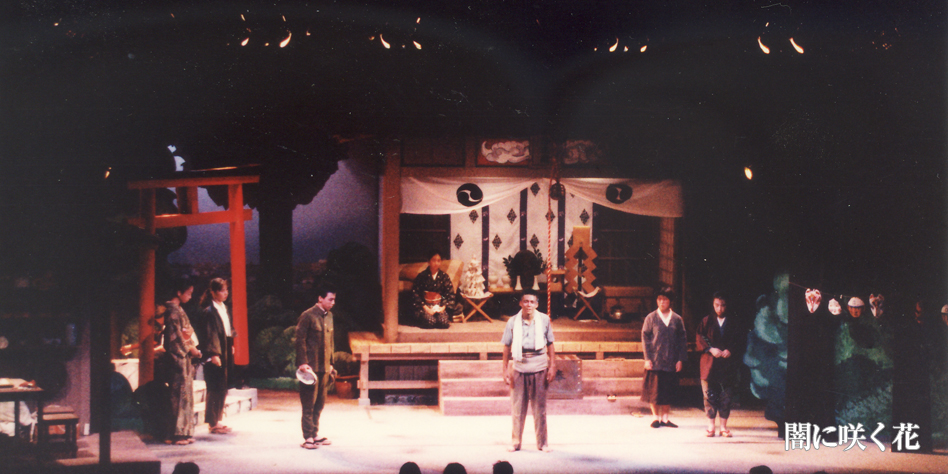|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008年9月20日(土)
一ヵ月半のブランクはあったが、今快調に『源氏物語』を訳している。
理由は、酷暑の夏が終わり文芸に格好の季節が到来したせいもあるが、なんといっても禁煙を止めたことによる。やはりわたしにはニコチンとタールは必須アイテムのようである。
さて、今は「絵合」の巻を訳している。目標より五巻ほど遅れている。
絵合わせとは、左方と右方の二組がそれぞれの物語絵を持ち出して、それぞれの作品を批評しながら優劣を決める催しである。
絵合わせは、歌合せから発祥しているが、古来から日本人は物を合わせる(競争させる)のが好きだそうで、特に平安朝の貴族社会では、「何々合わせ」といって歌や絵のほかにいろいろな物を合わせたそうである。貝合わせなどもそのいい例で、相撲も古代からの〈合わせ〉の系統を引くものである。
わたしは幼児の頃から相撲が好きだった。
幼児ながらも新聞の取組表を欠かさず見て、相撲巡業がある時は必ず見物に行った。
ファンだったのは栃錦で、その眼光の鋭さと、いつでも立つぞという気迫の仕切りが好きだった。昭和の名勝負といわれる大内山との一戦では、大内山の猛突っ張りをしのいで最後には首投げで勝利するのだが、これがパラパラ漫画になっていて、よくそれを見ては相撲の一発逆転の技を何度も何度も体感したものだ。
じぶんでも相撲をとり、幼児の頃はほとんど負けなかったので、
「相撲取りになる!」
と親に言ったら、
「おまえのようなチビではなれない」
と笑われ相手にされなかったが、それでもわたしは母親の美登利という名前から『勇緑』という四股名をつけて神社主催の相撲大会に出場した。
わたしが蔵前国技館ではじめて相撲を見た時の感想は、
「これはスポーツではなく、まるで芝居だな」
だった。番付が低い力士の取り組みには、観客は立ったり歩いたり、しゃべったり、飲み食いしたりして勝手に騒いでいるのに、番付が上がっていくとともに、しだいに静かになって土俵に集中していく。
それもそのはず、番付の上の力士は、塩を撒くのも、四股を踏むのも、一挙手一投足が絵になっているからだ。
わたしにとって力士とは
「まさに歌舞伎役者であり、三役になるということは体力の強さや技の巧みさのほかに、名優が持っている演技の貫禄を併せ持っていることなんだな」
と知った。
その時に見た千代の富士の足を高々と上げる四股は、まさに名優の境地に達していた。
相撲界は今や、さまざまな不祥事で揺れに揺れている。漫画家のやくみつるなどの識者がそれぞれの見解を述べているが、わたしは不祥事の大元は相撲の世界マーケット化にあると思っている。
だからわたしは、相撲はスポーツという見方から神事という見方にシフトを変えて、もう一度根本から考え直したほうがいいと思っている。外国人力士には日本古来の伝統を徹底的に教えるべきである。
外国人力士はアキハバラには行ったと思うが、歌舞伎は見ていないだろう。
まず外国人力士に歌舞伎を見せる。
こういう精神教育が一番だと思うけど、とても採用してくれないだろうな・・・・・・
2008年9月12日(金)
先日、ある女性がにこやかな顔をして事務所を訪ねてきた。
それもそのはず、難関を突破して某テレビ局の入社試験に合格し、来春からアナウンサーになるそうだ。
彼女は、かつて『モモ』から『12th Night』まで、わたしの7本の演出作品に出演してくれた子だが、一緒に作品を作り上げた同志としてほんとうに嬉しい。
おめでとう!
彼女は一時間ほど事務所にいて帰っていったが、こういう若い人(22歳)とつかの間でも談笑のひとときを持つのは楽しいものだし、ためになる。
現在の生活や就職試験の内容や就職状況を聞いたりした後、卒論の話になった。ドイツ文学専攻だから、
「ミヒャエル・エンデにしようと思っている」
と彼女が言った時、わたしはこの若い女性とわたしとのはてしない距離を感じた。今、
「ミヒャエル・エンデの作品を演出してくれ」
と頼まれたら、わたしはきっぱりと断るだろう。なぜならわたしにとっては今やミヒャエル・エンデの思想は無効になっているからだ。ミヒャエル・エンデの思想ではこの現在の逼迫した混沌とした状況は解決できない、とわたしは思っているからだ。だから、わたしは、
「エンデよりトーマス・マンにしたら?」
と、『魔の山』や『ヴェニスに死す』や『ブッデンブローク家の人びと』を著したわたしの大好きな作家をすすめたが、すすめた先で後悔した。やっと就職試験に合格して、これから満開に花咲こうとする若い人にトーマス・マンのような〈毒の華〉をすすめてはいけないと思ったからだ。
「エンデでいい、エンデでいいよ」
と、慌ててわたしは撤回した。
思えば、世の中がめまぐるしく変わると同時に、そして年齢を積み重ねるごとに、わたしもめまぐるしく変わった。
今やわたしには日本人が切っても切り離せない。
日本人を問う劇を創らなければ!
『源氏物語』創作は、そんなわたしの絶体絶命の所産になるだろう。
2008年9月11日(木)
『源氏物語』の主人公である光源氏は、学問上の知識と高い見識を持っているが、書の達人でもある。
その筆跡の見事さは、さまざまな場面で作者がしばしば取り上げている。そして光源氏の書の腕前に勝るとも劣らないのが、源氏の愛人である物の怪に変化する六条の御息所である。
このように平安貴族のステイタスを決めるひとつの要因に、字の上手さがある。和歌の贈答が恋のステップホードであった平安時代なのだから、恋人たちはせっせと書の修行に励んだことだろう。光源氏がまだ幼い若紫に書の手ほどきをする場面などそのいい例で、光源氏が若紫に手取り足取り教えるのは、じぶんの妻としての将来の確固としたステイタスを見据えた上でのことである。
ところで昨日、五人の政治家が自民党総裁選に出馬した。さっそくNHKで、五人の候補者が政策のキーワードを書いたボードを持って、それぞれの政策を語っていたが、この政治家たちの筆跡にわたしは唖然とした。
光源氏のような書の達人は一人もいないのだ。
いやそれどころが、五人が五人ともなんともいえない稚拙な字を書いていた。 誤解されると困るのであらかじめ断わっておくが、わたしは、
「稚拙な字がいけない」
とか、
「字が下手だから総裁にはなれない」
などと言っているのではない。稚拙な字と頭脳は比例しないし、頭脳明晰な科学者はがいして字が下手だし、達筆な人だっていい政治をしてくれるとはかぎらないからだ。
ただわたしは一人の文化人として、書という古来からの日本文化の伝統がこの政治家たちには受け継がれていないのに愕然としただけなのだ。つまり、何千年という書の伝統が、2008年の段階で遮断しているという歴史的事実に驚愕したのだ。この五人の政治家は、五人が五人共、初日に選んだ〈勝負服〉を身につけて会見に臨んでいたが、
「洋服だけでなく、〈書〉にも気を使ってもらいたかった」
というのがわたしの偽らざる感想である。
書とは、いうまでもなく字の上手さだけでなく、その配置の妙だ。
「白いボードにいかに黒マジックの文字が配置されているか?」
そんな期待をしてテレビを見ていたのだが・・・・・・・。
思えば昔、NHKの大河ドラマで『太閤記』があった。その中で秀吉に扮した緒形拳さんが、
「露と落ち 露と消えにし わが身かな 浪速のことも 夢のまた夢」
と、秀吉辞世の句を綴る。
その見事な筆さばきと字のなんと達筆なことだったか!
これがわたしたち演劇人のいう〈劇のリアリティ〉というものである。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|