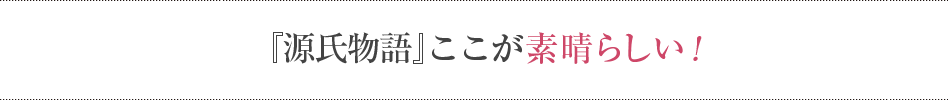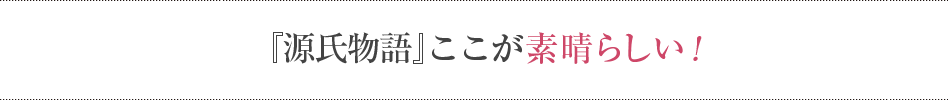|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
喪服の大君と心に喪服をつけた薫との愛恋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
このように心細い頼りないお住まいでは、好色な男だったら忍び込むのになんの支障もなさそうなので、中納言は、
〈わたし以外に訪ねてくる人がいたら、このまま大君になにもしないわけがない。そんなにことになったらどんなに悔しいだろう〉
と今まで悠長にかまえていたことまで不安になって、
〈この機会に大君と・・・〉
と思われるものの、大君のどうしようもなく辛い、と思って泣いていらっしゃる様子がかわいそうでならないので、
〈こんなに嫌がるのではなく、しぜんと心を開いてくださる時もあるだろう〉
と思い続けていらっしゃる。中納言は無理強いするのも心苦しいので、品よくお慰めになる。大君は、
「こんなことをする人とは思わないで、世間から疑われるほどいつも親しくしてきましたのに、不吉な喪服にやつれた姿をすっかりごらんになった思いやりのなさに、わたしの至らなさも思い知らされましたので、なにを言われても慰めようがありません」
と恨まれて、人に見られるとも思わないで着ていらっしゃった喪服姿が灯火の光で見えるのが、とても体裁が悪く、
〈辛い〉
と思い乱れていらっしゃる。中納言は、
「まったくこんなにわたしを嫌われるのは、
〈なにかわけがあるのか〉
と気がひけてなんとも言いようがない。喪服の袖の色を口実になさるのは無理もないけれど、長年ごらんになっていたわたしの気持ちを思えば、そんな喪中の遠慮など、今はじまった恋ならともかくわたしの場合必要ありません。『至らなさを思い知らされた』なんて、そんなこと考えないほうがいい」
とおっしゃって、あの琴の音を聞いた有明の月明かりからはじまって、時を重ねて大君を想う気持ちが抑えがたくなってきたのを、綿々とお話しになるので、大君は、
〈そんな恥ずかしいことがあったのか〉
と嫌になり、
〈そんな下心がありながら、知らない顔をして真面目そうにしていらっしゃったのか〉
と、なにもかも不快な思いで聞いていらっしゃる。
中納言はそばにある低い几帳を、仏から見られないよう仏前との隔てにして、形ばかり大君に寄り添って横になられる。名香(仏前に焚く香)の匂いがとても香ばしく漂い、樒(しきみ)が強い香りを放っているので、人一倍仏を信仰していらっしゃる中納言は気がとがめて、
〈喪中の今、まるでこらえ性もなく軽々しく振舞うのは、俗世を厭い仏道を志した当初の気持ちにも反するからやめておこう。宮の一周忌が明ける頃には、いくらなんでも大君のお気持ちも、少しはやわらぐだろう〉
などと、つとめて冷静になろうとしていらっしゃる。秋の夜の風情は、こんな山里でなくても、しぜんと感慨深いことが多いが、ここではなおさら峰の嵐も垣根の虫も、ただもう心細く聞こえてくる。中納言が無常の世の中のことをお話しになると時々受け答えなさる大君の様子は、見るべきところが多く感じがよい。大君が呼んでも寝ていた女房たちは、
〈大君と中納言は契りを交わされたのだ〉
とお二人の様子を察して、みな奥へ入ってしまった。大君は父宮がおっしゃったことなどを思い出されると、
〈なるほど、生きていると、じぶんの意志に反してこんなとんでもない目に会うのか〉
と無性に悲しくて、涙がとめどもなく流れ、宇治川の水の音に涙をそそられる気持ちがなさる。
いつのまにか明け方になった。お供の人が起きて咳払いをし、馬のいななく声に、中納言は旅宿の朝の様子を人が話していたのを想像なさって、興味深く思われる。夜明けの光が射してくるほうの襖を押し開けられて、しみじみと心にしみる空の景色を大君と一緒にごらんになる。大君も少しにじり出ていらっしゃると、奥行きも狭い軒先なので、忍ぶ草にかかっている露がしだいに光り輝くのが見える。お互いに、とても優美な容姿をごらんになって、中納言が、
「何をするというのではなく、ただこのように月も花も、心を一つにして楽しみ、はかないこの世の出来事を話し合って過ごしたい」
と、とてもやさしい様子でお話しになるので、大君はしだいに恐ろしさもやわらいで、
「こんなふうに面と向かってではなく、物越しでお話しするのなら、ほんとうによそよそしくはしないのですが」
とお答えになる。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|