|
|
|
|
|
|
|
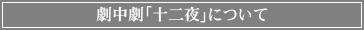
�@
�@�n�����b�g�����҂̈�c�����ĕ��̎E�Q��ʂ���҂ɉ���������Ƃ���������A�uHiroshima HAMLET�v�ł̓n�����b�g���g�����҂ɂȂ��ĉ�����Ƃ����ӂ��ɉ��ς����B
�@�����Ŗ��ɂȂ�̂��A�n�����b�g�͂Ȃ�̌������Ċ����̗܂𗬂��A�ŋ����v�����������g�ʼn����邩�Ƃ������Ƃł���B�n�����b�g�������ŋ��͎��̍����A�ǓƂȃn�����b�g�̋����ƃ����N������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B�͂��߂킽���̓V�F�C�N�X�s�A�̍ō�����ł���w���A���x�̗��̏�ʂ�z�肵�Ă������A�o�D�̋Z�ʕs���Œf�O���A�����V�F�C�N�X�s�A����́w�\���x�ɕύX�����B
�@�w�\���x�͂���܂Łu�����������̏\���v�u���ρE�\���v�Ə㉉���Ă��āA�w�\���x�ɂ́A�����j��ɎW�R�ƋP���V�[�������邩��ł���B�j���������@�C�I�����V�U�[���I�Ɩ���ς��A�����Ɉ�������݂ɁA���Ԃ�̎o�Ƃ����ˋ�̐l���i���͎������g�j�ɑ����Ĉ������Ƃ��낾�B
�����@�V�U�[���I�A������x�A���̐l�̂Ƃ���֍s���I�@���Y���̒n������Ȃ��B���ꂪ�䂩���̂̓I�����B�A���̐l���ƌ����Ă���I
���@�C�I���i�V�U�[���I�j�@�����Ȃ��ƌ���ꂽ��H
�����@���������Ȃ��B
���@�C�I���@�ł������Ȃ��ẮE�E�E�������鏗���A���Ȃ��������A�ꂵ��ł�̂ɁA�����Ȃ��ƌ���ꂽ��H
�����@����ȋꂵ�����ɑς����鏗�Ȃ�����̂��I�@���̈��͂����ۂ��Ȃ��́B����̈��͊C�̂悤�ɐ��܂����B�܂�̈��Ƃ͔�r�ɂȂ��B
���@�C�I���@�ł��m���Ă��܂��A�킽���́B�ɂ��قǁB
�����@�Ȃɂ����H
���@�C�I���@���̈����ǂ�Ȃ��̂��I�@�������Ă킽�������j�ɗ��܂���E�E�E���̖����A����j�������܂����B�킽�������Ȃ�A���Ȃ����������悤�ȁA�[�����ł����B
�����@�E�E�E�ŁA�ǂ��Ȃ����H
���@�C�I���@�����̂܂܂ł��B����ɂ�����ł������Ȃ��ŁA�o���̂ڂ݂ɑ����������A�Ԃ̖����ނ���ł䂭�悤�ȕБz���ɁE�E�E�ЂƂ�Y�̂ł��B�@�����āA�������ɂ��Ă䂫�E�E�E�����߂��J���ɒ��݁E�E�E����ł��A�̑��̂悤�ɐh�������A�߂��݂ɑς��Ă��܂����E�E�E���ꂪ�ق�Ƃ��̗��ł͂���܂��H�@�킽�������j�͂₽��Ɛ����𗧂Ă܂��B�ł�����́A�������������̂��́B�S�ɂ��Ȃ����Ƃ���ŁA���ł͂���܂���B
�����@�E�E�E
���@�C�I���@�s���Ă��܂��B
�����@�����E�E�E
�@���@�C�I���͗��̎g���ɍs���B
�����@�i�S�ł���āj�E�E�E�ŁA���̖��͗��Ɏ��̂��H
���@�C�I���@�E�E�E���͂킽����l�ł��E�E�E�킽����l�������Ȃ��̂ł��B
�@���̃��@�C�I���̌��t�́A���Ŕ������B���������Œ��ڂ��ׂ��́A���̌��t�̓��قȉ����I���ʂ��B�@�����Ń��@�C�I���́A�P�Ɍ��݂ɓ`���͂��̂Ȃ������������Ă��邾���ł͂Ȃ��B���ۂɕ���ɗ��������Ă���ޏ����g�̎p���A���Ԃ�̌���ɂ���Č`�ۉ����Ă���̂ł���B����������Ȃ�A����̂ނ��o���z����̃C���[�W���A���̂܂܃��@�C�I���̎p�ɓ��e����A�ޏ����g�����̃^�u���[�i�Î~��j�ƂȂ��Ă���B�܂�A������ɗ����Ă��郔�@�C�I���́A���̂܂ܒ��ɐH���r�炳��Ă���o���ł���A�߂��݂ɑς��Ă���u�E�ς̑��i�Α��j�v���̂��̂Ȃ̂ł���B

�@�w�n�����b�g�x�ɂ́A������q��r�������B�w�n�����b�g�x���㉉����ꍇ�A�킽�������͂��́q��r�������āA�����\�������肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�u�̏�v������܂Łq��r�Ƃ���Ă�����ʂł���B
�@�u�̏�v�́A�n�����b�g����e�ւ̕s�M���珗�������ɂȂ��āA���l�̃I�t�B�[���A�Ɂu�֍s���v�Ƃ������Ƃ���A���������Ăѕ�������Ă��邪�A����ł́A���̖{�������������K�ȕ\���ł͂Ȃ��̂ŁA�����ł́u���ݕ����̏�v�Ƃ������Ƃɂ���B
�@�u���ݕ����̏�v�́A�n�����b�g�������̉Ɛb�ł���|���[�j�A�X�̖��I�A�B�[���A�Ɏ������ċ������炵���̂ŁA�����ƃ|���[�j�A�X���n�����b�g�ƃI�t�B�[���A�̓�l���b���̂𓐂ݕ������āA�n�����b�g�̐^�ӂ��m�߂�Ƃ���ł���B
�@���̏�ł�����u��v�Ƃ���Ă���̂́A�n�����b�g�͂ӂ���̓��ݕ����ɋC�Â����̂��A�C�Â����̂Ȃ�A����͂����A����Ƃ��A�܂������C�Â��Ȃ������̂��A�Ƃ������Ƃł���B
�@����܂ł̃n�����b�g�㉉�ł́A�����������̓�ʂ�̉��߂��Ȃ���Ă����ƁA���c���Y�u�́w�u�̏�v�̃n�����b�g�x�ŏq�ׂĂ���B
�@�@�@�I�t�B�[���A���n�����b�g�ɑ�����Ԃ��Ƃ��A���̌��t���C��ł��Č`���I�ł��邱�Ƃ���A���q�Ȓ��ϗ͂ɂ������n�����b�g�͓��ݕ���������Ă���̂��@�m�����Ƃ������߁B�i�G�h���[�h�E�_�E�f���A�f�E�q�E�G���I�b�g�A�b�E�i�E�V�b�X���A��R�r�ꓙ�j �@
�@�A�@�n�����b�g���I�t�B�[���A�ɓs���������߂Ă���Œ��ɁA�A���X�̓�����ڂɂ��āA�u����͂ǂ��ɂ���H�v�Ƃ����ˁA���ݕ���������̂̑��݂�m�����Ƃ������߁B�i�n�[���[�E�O�������B�����o�[�J�[�A�i�E�v�E�h���[�p�[�A�f�E���C�����Y�A�f�E�a�E�n���X�����j
�@���Ƀ����E�M�u�\�����A�P�l�X�E�u���i�[���A吐�K�Y���A�c�����A�����̃n�����b�g�����̇@�ƇA�̉�������ŏ������Ă���B����吐�K�Y�́A���̏�ł킴�킴�L�X�V�[����ݒ肵�āA�I�t�B�[���A���n�����b�g�ɃL�X����āA���̂��Ƃ�e���猩��ꂽ�Ǝv���čQ�Ă�̂ŁA�n�����b�g�����ݕ����̑��݂ɋC�Â��Ƃ������o�����Ă���B
�@�͂����āA���E�I�ȑ�X�^�[��V�F�C�N�X�s�A���ҁA������{�̐l�C���o�Ƃ̉��߂͐������̂��H
�@�����A�����̂悤�Ƀn�����b�g�����ݕ����ɋC�Â����̂Ȃ�A���̏�ʂ́A�����ƃ|���[�j�A�X���d�|����㩂ɑ��āA�n�����b�g������㩂��d�|����Ƃ�����d�\���̏�ʂɂȂ��Ă��܂��B����l�Ȃ�܂������A16���I�̃V�F�C�N�X�s�A���ق�Ƃ��ɂ���ȕ��G�Ȃ��Ƃ��������������̂��H
�@�������V�F�C�N�X�s�A�͂���Ȃ��Ƃ͏����Ȃ������B�@�̉��߂��A�̉��߂����ł���B�n�����b�g�́A�����ƃ|���[�j�A�X�����ݕ��������Ă��邱�ƂɁA�܂������C�Â��Ȃ������̂ł���B
�@���̗��R���A���c���Y�u�͂ӂ������Ă��邪�A������킽���Ȃ�ɉӏ������ɂ��Ă݂�ƁA
�@�@�@�V�F�C�N�X�s�A���\�Ƃ���G���U�x�X�������̓����Ƃ��āA�u���ݕ����̏�v�ɂ͂ЂƂ̃��[��������B�܂蓐�ݕ�������҂́A���̂��Ƃ�K���ϋq�Ɍ��t�œ`���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��B���Ƀn�����b�g�ɂ����Ă��A�|���[�j�A�X�͂��ꂩ�瓐�ݕ������邱�Ƃ��u�����֖���A��Ă��āB�É��Ƃ킽���͕NJ|���ɉB��ē�l�̗l�q���v�Ƃ͂����茾���Ă���B�����炱�̓����̉����̃��[���ɏ]���A�����n�����b�g�����ݕ����ɋC�Â����̂Ȃ�A���̂��Ƃ��͂����肶�Ԃ�̌��t�Ŋϋq�Ɍ����Ă���䎌�Ȃ�T��������͂��ł���B�Ƃ��낪����̂ǂ���T���Ă��A����Ȍ��t�͌�������Ȃ��B���������āA�n�����b�g�͓��ݕ����ɋC�Â��Ă��Ȃ��B
�@�A�@���́u���ݕ����̏�v�������̊�{�ł���W���Ƃ������Ƃōl���Ă݂�ƁA���̏�̊W���́q�������ҁr�Ɓq�����ҁr�ł���B�����āA���̊W�����A�����E�i�킽�������̐����������Ƃ͂��������z�̐��E�j�ɂ����Đݒ肷��Ƃǂ��Ȃ�̂��H�q�����ҁr�́q�������ҁr���牽�������̂��H�@�����ō����ƃ|���[�j�A�X���n�����b�g�ƃI�t�B�[���A�Ƃ̘b����m�肽���̂́A�n�����b�g�̋��C�̌����������̂��߂Ȃ̂��A����Ƃ������������Ȃ̂��Ƃ������Ƃł���B����̐��E�ł́A���ݕ������Ă���҂̊��҂𗠐��āA�������҂����̊W���Ȃ��b��������A�Ȃɂ�����Ȃ��őf�ʂ肷�邱�Ƃ����肤�邪�A���̐��E�ł͂���͋�����Ȃ��B�ЂƂ��сu���ݕ����̏�v��ݒ肵���̂Ȃ�A�K�����̂悤�Ȃ��Ƃ���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂�q�������ҁr�͖��ӎ��Ɂq�����ҁr�̊��҂���A���邢�͋���Ă��錾�t������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����łȂ���A�u���ݕ����̏�v�͌��Ƃ��Đ������Ȃ��B�����̗v�ł���W������l���Ă��A�u���ݕ����̏�v�́q�����ҁr�Ɓq�������ҁr�Ƃ����A�������ĒP���ȍ\���ł����Ȃ��̂ɁA����܂ŃV�F�C�N�X�s�A�w�҂⌤���Ƃ����́A��������Ƃ��畡�G����ɂ��āA�����u��v�����������̂悤�ɕT�����ӂ�܂��Ă����B
�u���ݕ����̏�v�̃n�����b�g�̑䎌�́A���c���Y�u�������悤�ɁA�u�ϋq�͒m���Ă���̂ɔނ��m��Ȃ��Ō�������A�h���}�`�b�N�E�A�C���j�[�Ƃ��Ă������낢�̂ł���v�B
�@�̏�v�́A�|���[�j�A�X���d�g�݁A�����Ɠ�l�ŃA���X�̂����ɂ�����A�n�����b�g�̃I�t�B�[���A�Ƃ̂��Ƃ�𗧂����������ł���B�����āA�n�����b�g�́u����͘������A���O�[���A��S�������v�Ƃ������Ƃ́A�ނ��牤�ʂ����ǂ肵�������̋����h�����낤���A�u����͂ǂ��ɂ���H�v�Ƃ����₢�����́A�|���[�j�A�X�̎������Η������A�u������������߂Ă����̂��ȁA�O�ɏo�Ă��Ȃ܂˂����Ȃ��悤�Ɂv�Ƒ����n�����b�g�̂��Ƃ���X�����������낤�B����́A��l�̑��݂ɋC�Â�������ł͂Ȃ��i�C�Â����Ȃ�Ȃ�������x��������悤�Ȃ��Ƃ�f�����I�j�A�h���}�`�b�N�E�A�C���j�[�Ƃ��Č�����̂ł���B
�@���̌��ʁA�����̓n�����b�g�̋��C�̌������u�W�Q���ꂽ��S�v�ɂ���Ɗ댯�����A�|���[�j�A�X�́u���₳�ꂽ���v�ɂ���Ǝ������m�F����B���ꂪ���̏�̌��I�ȈӖ��ł���B�����m��̂́A�n�����b�g�ł͂Ȃ��A�ϋq�Ȃ̂ł���B
�i���c���Y�u�u���ƃ��[���A�@�C�M���X�����m�[�g�v�j
�@���c���̉𖾂����Ƃ���ł���A����ȊO�̉��߂͂��肦�Ȃ��̂ɁA�����a�q�́A�͍����Y�Ƃ̑Βk�u���ǃV�F�C�N�X�s�A�v�ŁA���������߂����Ă���B�����́A�I�t�B�[���A���������n�����b�g�ɕԂ��Ƃ��ɁA���Ԃ��u�i�ʂԎ҂ɂƂ��ẮA�ǂ�ȍ����ȑ������A�����̐^�S���Ȃ��Ȃ�݂��ڂ炵���Ȃ��Ă��܂��܂��v�́u�i�ʂԎҁinoble�@mind�j�v�Ƃ������t�������Ȋ����Ȃ̂ŁA�����ƃI�t�B�[���A�炵�������ɕς��悤�Ǝv���āA�n�����b�g���̐^�c�L�V�ƃI�t�B�[���A���̏������q�ɁA���̂��Ƃ������˂��Ƃ���A
�����@�i�O���j����������A�����A���͂��̌��t�͕��e�Ɍ��킳��Ă���Ǝv���ĉ����Ă��܂��A�ƌ�������ł��B�^�c��������āA�l�͂���������邩��ӂ��ƐS���₦�āA���ɂ��₶������ȂƎv���A�u���O�͒�i���H�v���Đq�˂�A�ƌ�����ł���B���͂����т����肵�Ă��܂��ĂˁB�����Ă݂�A���ʂ��ł��B�ꖋ�O��ŃI�t�B�[���A�̓|���[�j�A�X�Ɂu�C���炢���������āv�Ƃ�����������Ă����ł�����B�V�F�C�N�X�s�A�͑䎌�̒��ɖ��҂ւ̂��������ߍ���ł����ł��B�܂�A�����ł��₵���Ǝv���A�ƂˁB���̏�ʂ͂˂ɖ��ɂ�����ł��B�i�����j�n�����b�g�͂���ɋC�Â��̂��A�C�Â��Ȃ��̂��B�C�Â��Ƃ�����Ȃ̂��B���ꂪ�˂ɖ��ɂȂ��ł���B���������ǂ����ŋC�Â��Ƃ������o���Ƃ��Ă܂�����ǂ��A�\�̂Ȃ����o�Ƃ��u�C�Â��v���Ƃ�\�����܂��ƁA�|���[�j�A�X�ƃN���[�f�B�A�X���B���u�ԂɃn�����b�g�������ė��Ėڂ̒[�ł�����ƌ��Ă��܂��A�Ƃ������o���Ƃ����肷��B�ł��A����noble
mind�������������ƕ�����A�ڌ�����K�v�͂Ȃ���ł��ˁB�����ɂ����ɉB��Ă���ƋC�Â��Ȃ��Ƃ��Ă��A�I�t�B�[���A�������̂��Ƃ�noble
mind �ƌ������r�[�ɁA�n�����b�g���u��H�v�Ǝv���悤�ɂł��Ă������B����͉������A���ɕ��e������ȁA�ƂˁB������a�����������܂܍����o�������t���A������Ɛ^�c����͂����ǂ�ł����������B�D�ꂽ���҂��Ă������ł���B���͂����܂œǂ߂Ȃ���������ǂ��A�I�t�B�[���A�炵���Ǝ����Ŏv���悤�ɁA���Ȃ��ĖĂ��܂�Ȃ����x�ɂ́A�n������Ȃ������ȂƁB�i�͍����Y�E�����a�q�u���ǃV�F�C�N�X�s�A�v�j
�@�͂����ď����̌����Ƃ���ł��낤���H�@
�@�킽���͂����͎v��Ȃ��B���̏�́A�����ߑ��̃V�F�C�N�X�s�A�̌��t�ɘf�킳�ꂸ�ɁA�n�����b�g�ƃI�t�B�[���A�Ƃ̂ӂ���̊W���A�܂葡�����q�Ԃ��ҁr�Ɓq�Ԃ����ҁr�Ƃ����W���ōl���Ă݂邱�Ƃ��B��������Εs���͂����ǂ���ɉ�����B
�@ �@����ł́A�����̉��߂������ɂ��̏�̌��I�{������͂���Ă��邩���A�킽���̑�{�ɂ������Ď����Ă݂�B�`�����������A��r�ł���悤�ɏ����̖|����ڂ��Ă������B
�n�����b�g�@�i�L����To be,or not to be.�̓Ɣ���j�������I�t�B�[���A�I�X�̗d���A�l�̍߂̎͂������̋F��ɂ��߂Ă���B
�I�t�B�[���A�@�a���B���̂���͂��@���������ł�������Ⴂ�܂����H
�n�����b�g�@���肪�Ƃ��A���C���挳�C�A���C�B �I�t�B�[���A�@�a���A���Ղ��������i�X�A�������Ԃ����Ȃ���Ǝv���Ă���܂����B�ǂ������[�߂��������B
�n�����b�g�@����A�ʖڂ��B��������������͂Ȃ��B
�I�t�B�[���A�@�a���A�悭�����Ă����ł̂͂��B�D���������t���Y���Ă��������Ē������i����w�L��v���܂����̂ɁB���̍���������܂����B���Ԃ��������܂��B�i�ʂԎ҂ɂƂ��Ă͂ǂ�ȍ����ȑ������A�����̐^�S���Ȃ��Ȃ�݂��ڂ炵���Ȃ��Ă��܂��܂��B�����A�ǂ����B
�n�����b�g�@�͂͂��I���O�͒�i���H
�I�t�B�[���A�@���H
�n�����b�g�@���O�͂��ꂢ���H
�i�����a�q��u�n�����b�g�v�j
�n�����b�g�@�X�̗d���A�l�̍߂��F���Ă���B
�I�t�B�[���A�@�a���B�ŋ߁A���̂̒��q�́H
�n�����b�g�@�������Ō��C���B
�I�t�B�[���A�@�������������́A�����Ƃ��Ԃ����悤�ƁB����肭�������B
�n�����b�g�@������������ڂ��͂Ȃ��B
�I�t�B�[���A�@����ȁI�D���������t�������Ă������������炤�ꂵ���āA���̍��肪���������͕K�v����܂���B�ǂ����B
�n�����b�g�@���܂��͒�i���H
�I�t�B�[���A�@�킽�����H
�n�����b�g�@���������H
�i�O�V��{�u�}�C�E�n�����b�g�v�j
�@��������a�����������u�i�ʂԎ҂ɂƂ��ẮA�ǂ�ȍ����ȑ������A�����̐^�S���Ȃ��Ȃ�݂��ڂ炵���Ȃ��Ă��܂��܂��v�́A�킽���̑�{�ł͍폜���Ă���B�Ȃ��Ȃ�A���̍����Ԃ����A�܂�����������䎌�͓�����O�̂��Ƃ������Ă��邾�������A�悤����ɃI�t�B�[���A�͑����͂����u�K�v����܂���v�ƌ����������������炾�B
�@���̌��Œ��ڂɒl����̂́A����Ȍ��t�ł͂Ȃ��A�n�����b�g�́u������������ڂ��͂Ȃ��v�ł���B �@
�@�I�t�B�[���A���瑡����Ԃ��ꂽ�B���������l�̃I�t�B�[���A���炾�B���̂Ƃ��̃n�����b�g�̋C�����́A�����ōl���Ă݂�����킩��B�܂莸���������Ƃ�������̂Ȃ�A���������ɑ�����Ԃ��ꂽ�o�����Ȃ��Ă��A����ɂ����đz���ł���B�n�����b�g�́A�V���b�N�ŋC�����]���Ă���ƁB���̋C�����́A�����炭����ł��������Ǝv�����A���̌�̔����ƂȂ�ƁA�l�ɂ���Ă������Ă���B�n�����b�g�̂悤�ɁA�u������������ڂ��͂Ȃ��v�ƌ������̂����邾�낤���A�������Ȃ�����Ėق��ė���������́A�܂��߂��߂��������́A���邢�́u�v�������āA������x�����Ă���v�ƈ��������ނ��̂����邾�낤�B���̐獷���ʂɂ��锽������A�V�F�C�N�X�s�A�́A�n�����b�g�Ɂu������������ڂ��͂Ȃ��v�ƌ��킹�邱�Ƃ�I�������B�����Ɍ��I�ȈӖ�������B
�@������Ԃ��ꂽ�n�����b�g�́A���܂�̃V���b�N�ɋC�����]����B���l�ɑ�����Ԃ��ꂽ�Ƃ���������F�߂����Ȃ��B�����瑡���͂��ĂȂ��Ƃ����Ӗ��Łu������������ڂ��͂Ȃ��v�Ƃ������A����ł��Ȃ��I�t�B�[���A���u����ȁI�D���������t�������Ă������������炤�ꂵ���āA���̍��肪���������͕K�v����܂���B�ǂ����v�ƁA���������悤�Ñ�����̂ŁA������ꂽ�S�͂���Ɏh������āA�I�t�B�[���A�炵���Ȃ�B�����ăI�t�B�[���A���̑��Ƃ��Ԃ点��B
�@�ڂ̑O�ɂ���̂́A���͂�u�V�g�̂��Ƃ��A�킪���̋����@���̉��g����i�����a�q��j�v�I�t�B�[���A�ł͂Ȃ��B�����͕�Ɠ����悤�ɒn�ɑ��Ă��܂����B������u���܂��͒�i���H�v�u���������H�v�Ɛu���̂ł���B
�@
�@���̂悤�ɁA�����̃n�����b�g�́A�����̒Ɏ肪���܂�ɑ傫�����߂ɁA�I�t�B�[���A�̂��Ƃ������ɂȂ��A�^�c�������悤�Ɂu���ɂ��₶������ȁv�ȂǂƂ͓��ꂨ������͂����Ȃ��B����ȋC���]�T�Ȃǂ܂������Ȃ��̂��B
�@�ɖ��𒍂��ꂽ�n�����b�g�̑����́A����ɉ����x�𑝂��Ă����B
�I�t�B�[���A�@�Ȃ�����Ȃ��Ƃ��H
�n�����b�g�@���܂�����i�Ŕ������Ȃ�A���̓�͈ꏏ�ɂ����Ȃ��ق��������B
�I�t�B�[���A�@�������ƒ�i�́A�悢��荇�킹�ł́H
�n�����b�g�@����A����������i�ȏ���s�ςɊׂ��B
�I�t�B�[���A�@�E�E�E
�n�����b�g�@�E�E�E���܂��������Ă��B
�I�t�B�[���A�@�킽�����E�E�E�����M���Ă܂����B �@ �@
�@�n�����b�g�̓I�t�B�[���A�ɃL�X�����悤�Ƃ���B�I�t�B�[���A�͖ڂ����B
�@���̊�Ƀn�����b�g�͌��t��f������B
�n�����b�g�@�c�O���ȁB�����ĂȂ��Ȃ������B
�I�t�B�[���A�@����ȁB �@ �@ �@
�@�n�����b�g���u�����Ă����v�ƌ����āA�����Ɂu�����ĂȂ��Ȃ������v�Ɣے肷��̂́A�I�t�B�[���A�ɑ�����Ԃ��ꂽ���Ƃւ̕����A���������Ƃ���ɂ킽���̓n�����b�g�̗c�������Ă��܂��B�n�����b�g�͑�l�ɂȂ�Ȃ����N�ł���B���̏��N�̌��Ȑ��́A�I�t�B�[���A��ے肷����肩�A�����̂��̂�ے肵�A�I�t�B�[���A��s�ς̕�Ƀ_�u�点��B�I�t�B�[���A�͂��Ԃ�𗠐����B�����ǓƂ̂��Ԃ�������Ă��A��܂��Ă��A�ނ�������₢�Ă�����Ȃ��B����ς�A���܂��͕�Ɠ����悤�ɁA�������炻�̒�ƌ�������悤�ȏ����B���̔������̒��ɂ͎����B��Ă���B��
���A���f���o��B
�n�����b�g�@���Ȃ�߂Ă��܂��I�Ȃ��ߐ[���l�Ԃ݂�����H�@����͂���ł��܂��Ƃ��Ȃ��肾���A����ł��ꂪ�Y��ł���Ȃ���悩�����Ǝv���قǍߐ[���l�Ԃ��B
�����ŁA���O�[���A��S���X�A�z�������ł܂����s�ł��Ȃ��߂�����Ă���B����Ȓj���V�n���������āA�������������ł���H���ꂽ���݂͂�Ȉ��}���B������M����ȁI�@���Ȃ�߂Ă��܂��I�e���͂ǂ��ɂ���H
�I�t�B�[���A�@�i�閧�����̂ł͂Ȃ����Ƃ��ǂ��ǂ��āj�ƂɁB
�n�����b�g�@���Ⴀ�A�����߂Ă����I�O�Ńo�J�Ȑ^�������Ȃ��悤�ɂȁB
�I�t�B�[���A�@�E�E�E
�n�����b�g�@������������Ȃ�A���Q������Ɏ̌��t������Ă��B���܂����X�̂悤�ɒ�i�ŁA��̂悤�ɐ����ł��A���Ԃ͂Ȃɂ��Ɣ���B���Ȃ܂����I�ǂ����Ă������������Ȃ�A�o�J�Ƃ���B�����Ȃ�͌����Ȃ��Ȃ�����ȁB���܂��������́A���h�肽����A�_���炳��������������ς���B�K��U��A�Â�����āA�u�m��Ȃ�������v�ȂǂƂʂ����B�i�L���āj�������܂�ł���I�������ŋC���������I�������A�����ȂǁA���̐���������ĂȂ��Ȃ�I���łɌ������Ă�҂͋����I�������Ă����Ă��B���̂ЂƑg�ȊO�͂ȁB���̎҂͐��U�Ɛg�ł���I
�@
�@�n�����b�g�͑��蕨�𓊂����đޏꂷ��B�I�t�B�[���A�́A�n�����b�g�������̂Ă����蕨�����邾���A�V���b�N�Ō��t�ɂȂ�Ȃ��B
�i�O�V��{�u�}�C�E�n�����b�g�v�j �@ �@
�@�n�����b�g���A�I�t�B�[���A�̕��̋��ꏊ�������˂���A������ے肵����A��ƍ����E�������Ƌ��Ԃ̂́A�����܂ł��Ȃ��A���ݕ������Ă���|���[�j�A�X�ƍ����ɂ��Ă��Ă���̂ł͂Ȃ��A�I�t�B�[���A���瑡����Ԃ���ď��������S���A�����������ƂȂ��ĕ��o���邩�炾�B����́A�n�����b�g����ɑ��ĕ����Ă��錙�����A�I�t�B�[���A���܂߂ď����ւ̑����ƂȂ邱�Ƃ������Ă��邪�A�n�����b�g�̑��������܂����̂́A�����܂ł����l�ɑ�����Ԃ��ꂽ�V���b�N�̔���p�ł���A�V���b�N���傫����Α傫���قǁA���������܂����Ȃ�͓̂��R�̂��Ƃł���B
�@���̂悤�ɁA�����̓n�����b�g�̃I�t�B�[���A�ɑ��鈤�������ɋ������������A�t���I�Ɏ�����ł���B���̋t���ɂ��n�����b�g�̈���\�����Ȃ�������A�ϋq�̓n�����b�g���Ɣ��Ō����u���Ȃ�Ȃ����̋ꂵ�݁v���A�I�t�B�[���A�̎���m���ė܂Ȃ���ɂ����u����͈����Ă��A�����Ă��A�I�t�B�[���A�������Ă��v���A���I�����������ĕ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�V�F�C�N�X�s�A�́A�����������悤�ɁA�u�䎌�̒��ɖ��҂ւ̂��������ߍ���ł���v�̂ł͂Ȃ��A�䎌�̒��Ɂq�����l���r�̂��������ߍ���ł���̂��B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

�@
�@�n�����b�g�́A���̖S�삩��A���͒�Œ��Q�̍Œ��ɒ�̃N���[�f�B�A�X�ɓŎE����A�����̍��Ɖ��܃K�[�g���[�h�i�n�����b�g�̕�j��D��ꂽ���Ƃ�����A���Q�𖽂�����B�n�����b�g�͋��l�̂ӂ�����Ă��̋@��������������A�₪�ĖS�삪�^�킵���Ȃ�A���Q�����߂���Ă��܂��B
�n�����b�g�@���������S��͈�����������Ȃ��B�����ɂ͕ω��̗͂�����l�̊�Ԏp�����Ƃ����B�����������牴���C��ɂȂ�A�J�T�ǂɂ������Ă��邹����������Ȃ��B�����͂����ɂ�����ʼn���f�킵�A�n���ɗ��Ƃ����Ƃ����̂��B �i�����a�q��u�n�����b�g�v�j �@
�@�S�삪�����Ȃ�A���݂̉��ł���N���[�f�B�A�X�͕����E���Ă��Ȃ����ƂɂȂ�B���͂ق�Ƃ��ɕ����E�����̂��H�@�S��̌��t��M���ĕ��Q���Ă����̂��H�@������������S��͎��݂����̂ł͂Ȃ��A�J�T�ǂɂ�錶�o��������������Ȃ��B�n�����b�g�́A�����̊m�邽�߂ɉ��̔��������悤�ƁA�����ŎE���ꂽ�Ƃ��̗l�q���ŋ��ɂ��邱�Ƃ��v�����B�ŋ��́A�͂��߂ٌ͖��ŁA�Â��đ䎌���ŏ㉉�����B
�@
�@�g�����y�b�g�̐��t�ɑ����A�ٌ����n�܂�B���Ɖ��܂��o�ꂵ�A�݂��ɕ��������B���܂͂Ђ��܂����A���̐����𗧂Ă邵����������B���͔܂𗧂��オ�点�A���̎��ɓ���������������B���͉Ԃ̍炭��ɐg����������B���܂͉����Q�������̂����͂��ė�������B�قǂȂ���l�̒j������A���̓����牤�������A����ɐڕ����A�����Ă��鉤�̎��ɓł𒍂��A���̏������B���܂��߂��Ă��A��������ł���̂ɋC�Â��Č������Q���B�ŎE�҂��O�A�l�l�̎҂��]���čĂь���A���܂Ƌ��ɔ߂��ނӂ������B���͉̂^�яo����A�ŎE�҂͉��܂ɑ��蕨�������o����������B���܂͂��炭�͂�Ȃ��f�U������邪�A���ɂ��̈��������B�ޏ�B
�I�t�B�[���A�@�a���A���܂̂͂ǂ��������Ƃł��傤�H
�n�����b�g�@���₠�A�����݂Ȉ����A�������݂��B
�I�t�B�[���A�@���̂��ŋ��̑e�̂悤�ł�����ǁB �@ �@
�@������o��B
�n�����b�g�@�����������Ă����B���҂ɔ閧�����ƌ����Ă��������A���ł������Ă��܂��B
�I�t�B�[���A�@���܂ٌ̖��̈Ӗ����H
�n�����b�g�@����A����ɂ��O��������ǂ�Ȃ��Ƃł��ڌ�����Ƃ��B���C�Ō�����������A���������C�������ȉ�������Ă����B
�I�t�B�[���A�@�����܂���A����Ȃ����Ȃ����Ƃ�����������āB���͎ŋ������܂��B
�������@����̉����܂����̔ߌ��A�ȂɂƂ�����������܂��Ă��Ò��̂قǁA�炵�Ă��肢�\���グ�܂��B�i�ޏ�j
�n�����b�g�@���ꂪ�O���ォ�A�w�ւɍ������H
�I�t�B�[���A�@�ق�Ƃ��ɒZ�����ƁB
�n�����b�g�@���̈��Ɠ������B �@
�@�����̉��Ɖ��ܓo��B
�����̉��@�z�̐_�t�B�[�o�X�̌䂷�n�Ԃ́A����O�\���с@�C�_�l�v�`���[���̒��H���z���A�n�̐_�e���X�̗�������@�O�\���\��d�˂����܂��̌� �́A���ւ̌�����@�O�\���\��d�˂������̍Ό��A���̌������Ƃ炵�������B���̎n�߁A����̐S�͈��Ɍ���@����̎�͍����̐_�n�C�����̐��Ȃ��J�Ō����B
�����̉����@���̂̂��X�ɗz�������A����̈��̉ʂ�܂Ł@�������H�����ǂ�Ƃ��B����ɂ��Ă������ɂށA�ߍ��͂��C���������ꂸ�@���˂Ă̂����C���ǂ��ւ��A�ʕς�菢����@�C������łȂ�܂��ʁB�Ƃ͐\���A�킽�����̋C������Ȃǁ@���قǂ̂��ƁA�ǂ������Ă��Ȃ����܂��ȁB�@���q�̋C������Ə�Ƃ���ɘA��Y�����́A�ǂ���̎v�����m�炸�ɂ��ނ��A��Ȃ���x���z�����B�킽�����̈��������قǂ��A���̂�����\�Ɍ��ꂲ�����̂͂��B�����[�܂�ɂ�C��������[�܂�܂��B�����̂�Ƃ��A���ׂȕs��������ƂȂ�@���ׂȋ���̋ɂ܂�Ƃ��A�����傫������́B
�����̉��@����A�]�����Ȃ��ɐ旧�͕K��A�����������炸�B�g���S�����͂āA�������s�����B���Ȃ��͂��̗킵�����Ɏc��@�h������A�Ȃ��炤�邪�悢�B���̐g�ɗ�炸�����l��v�Ɍ}���\
�����̉����@�����A���̐�͕����Ƃ��Ȃ��B���̂悤�Ȉ��͂��̋��̗���B��v�ɂ܂݂��Ȃ炢�������ꂽ���B��x�ڂ̕v���}����́A���߂̕v������߂����B
�n�����b�g�@�i�T���j�ꂢ���A���܂̌��t�B
�����̉����@�č��������̂����͗��������ނ�ڂ����S�A�����Ĉ��ł͂������܂��ʁB���Ƃ˂ɂē�x�ڂ̕v�̌��Â�����͖S���v���Γ�x�܂ł��E���ɓ������B
�����̉��@���Ȃ��̐S�A���t�ǂ���ƐM���悤�B����ǁA�����Ɍ������ӂƂāA�Ƃ����j�邪�l�̏�B�u�Ƃď��F�͋L���̂����ׂɂ������A�Y���͍��炩�Ȃ�ǐ������͂͊o���Ȃ��@���ł����}�𗣂�ʐ��ʎ����A�n������̂�����n�ɗ�����B����ɉۂ����镉�́@�x�������O����͓��R�B�M���v���ɂĖڎw�������Ƃ��@�v������߂�Ώ���������B�߂��݂����т��A���̌������̋ɂ݂ɂā@��Ă����Ƃ�ł��B���т̒����ɒB����Ƃ���A�߂��݂͓ޗ��ɗ����A���ׂȂ��ƂŔ߂��݂͊��тɁA���т͔߂��݂Ɏp��ς���B���̐��͖���Ȃ�A����̈��ƂĂ��@���̉^�Ƌ��Ɉڂ남���Ɖ��̕s�v�c������͂��ʁB���Ǝ��̉^�A�����ꂪ����������@���ꂼ�����������ʖ₢�B�ʍ����ҁA�Ⴋ�ɗ���Β��b����������@�n�����ҁA�n�ʂ��オ��ΓG�������ɕς��B�����̂��Ƃ����͎��̉^�ɏ]���B�����ɂ���ҁA�F�ɂ��ƌ������A�t���ɂ���ҁA���Ȃ��F�����߂�������܂��G�ɕ^�ς��B�Ƃ܂ꏉ�߂ɗ����߂�b�����ׂA����̈ӎu�Ǝ��̉^�Ƃ݂͌��ɔw������̈Ӑ}�͏�ɕ������B�v���͉䂪���̂Ȃ�ǁA���̎���͉䂪���̂Ȃ炸�B��v�ɂ܂݂��ʂ��Ȃ��̌��ӂ��@�ŏ��̕v�̎��ƂƂ��Ɏ��ɐ₦�悤�B
�����̉����@�������A���Ƃ���n���Ƃ��b�܂��A�V������^�����A���̊y���݁A��̈��炬��D���A�M���Ɗ�]����]�ɕς��A�悴�����ɂȂ��ꐢ�ԂƂ̌�����f����悤�ƁA���т̊�𑓂��߂����邠��Ƃ�����Ђ����K������Ƃ̊肢��ł��łڂ��A���̐��݂̂����̐��܂ʼni���̋ꂵ�݂����Z�����ƁA�ЂƂ��щǕw�ƂȂ�Γ�x�ƍȂɂ͂Ȃ�܂��ʁB
�n�����b�g�@�����������̐�����j������B
�����̉��@�悭���������B�������܁A���炭�ނ��Ă���B�C����ꂽ�B���̗J���ߌ�̂ЂƎ��@����ŕ���킵�����B
�����̉����@���肪���ނ����₵�Ă���܂��悤�B�Ў��������l��܂��ʂ悤�B�i�ޏ�B���͖���j
�����@���̂��܂̐����͂��ǂ�����悤�ˁB
�n�����b�g�@����A���������Ƃ͎��ł��傤�B
���@�؏����͕����Ă���̂��H�@���������͂Ȃ����낤�ȁH
�n�����b�g�@�����A�����A�������V�т݂����Ȃ��̂ł��\�ŎE�������B���������Ȃǂ���܂���B
���@�O��͂Ȃ�Ƃ����̂��H
�n�����b�g�@�u�˂��ݎ��v�\����A���ɂ�����g���I���̎ŋ��A�E�B�[���ŋN�����E�l�����ƂɂȂ��Ă��ā\����̖��̓S���U�S�[�A����v�l�̓o�v�e�B�X�^�\�����ɕ�����܂��B���ɂӂ炿�Ȋ�݂��A�������ꂪ�ǂ������B�É���A�S���k�����Ƃ���̂Ȃ���X�ɂ́B�ɂ������䂭���Ȃ��B���ɏ����n�����Ђ�߁B���̂Ȃ��g�͕��C�̕����B
�@ �@
�@���V�A�[�i�X�o��B
�n�����b�g�@���̒j�̓��V�A�[�i�X�Ƃ����āA���̉��ł��B
�I�t�B�[���A�@����̂悤�ɂ悭�������ł��ˁB
�n�����b�g�@�l�`���̔G���������Ă����A���̐l�`�����O�Ƃ��O�̗��l�Ɍ����āA��l�̒�����邱�Ƃ����Ăł���B
�I�t�B�[���A�@�����܂���A�a���A����Ȃ����Ȃ����Ƃ�����������āB
�n�����b�g�@�����Ƃ����Ȃ����Ƃ�������A���O�͒ɂ����Ă��߂����낤�B
�I�t�B�[���A�@��������߂ɂȂ��āB
�n�����b�g�@�a�߂�Ƃ����A�Ȃǂƌ����ĕv���}���A���Ԃ炩���B�\�������Ƃ��A�l�E���B���������Ԃ��������ߖʂ͂�߂āA�n�߂�B�����A�u���킪�ꐺ�̑�K���X�A���Q����Ƌ��т���v�B
���V�A�[�i�X�@�Â���݁A�r�͖�A�ł������A���͍��@�܂�悭������ɐl�ڂ��Ȃ��B�Ŗ�̑����i�肵�Ŗ�@�����̎��O���юA�O���ѓŋC�𐁂����܂�A�������낵���V�R�́A���͂����肵�ғłŌ��₩�Ȃ閽�A�������ɒD���B�i���錀���̉��̎��ɓŖ���������j
�n�����b�g�@�뉀�ʼn���ŎE���A���ʂ�D���̂ł��B���̖��O�̓S���U�S�[�B���̘b�͍����c���Ă��āA�I�蔲���̃C�^���A��ŏ�����Ă���B�����A�����������̐l�E���̓S���U�S�[�̔܂������������܂��B
�I�t�B�[���A�@���l���������ɂȂ�B
�n�����b�g�@�ق��A��C�ɂ��т������H
�����@���Ȃ��A�ǂ��Ȃ������́H
�|���[�j�A�X�@�ŋ��͎~�߂�B
���@����������āB���ցB
�|���[�j�A�X�@���肾�A���肾�A���肾�B�i�n�����b�g�ƃz���C�V���[���c���A�S���ޏ�j
�i�����a�q��u�n�����b�g�v�j
�@
�@�ٌ��ł͂Ȃɂ��������Ȃ����������A�䎌���̓ŎE��ʂŐȂ𗧂��ލ����Ă��܂��B���̉��̔��������āA�n�����b�g�͖S��̌��t�͐^���ł���A��������ŎE�������Ƃ��m�M����B
�@
�@�����Łu��v�Ƃ���Ă��邱�Ƃ�����B����������Ă݂�ƁA
�@�@�@�Ȃ������悤�ȓ��e�̌����A�q�ٌ��r�Ɓq�䎌���r�Ƃ��āA��x���J��Ԃ����̂��H
�@�A�@�Ȃ����́A�ٌ��̓ŎE��ʂŔ������Ȃ��̂��H
�@�B�@�Ȃ����́A�䎌���̓ŎE��ʂőލ�����̂��H �@
�@�����́u��v���������߂ɂ́A�܂����̏�ʂ��q�ŋ��r�Ɓq�����̌����r�Ƃɋ敪�����Ă݂�K�v������B���̏�ʂ͂��̂悤�ɂ킯�邱�Ƃ��ł���B
���ŋ��i�ٌ��j
�������̌����i�I�t�B�[���A�̔����j
���ŋ��i�䎌���E���܂̐����j
�������̌����i�n�����b�g�̕�ւ̂��Ă��j
���ŋ��i�䎌���E���܂̐����j
�������̌���(�n�����b�g�̕�ւ̂��Ă�)
���ŋ��i�䎌���E���܂̐����j
�������̌����i���܂̔����j
���n�����b�g�̊��荞�݁i�����̈ÎE�҃��V�A�[�i�X�̏Љ�j
�������̌����i�I�t�B�[���A�����炩���j
���n�����b�g�̊��荞�݁i�l�E���̍Ñ��j
���ŋ��i�䎌���E���V�A�[�i�X�̓Ɣ��ƓŎE��ʁj
���n�����b�g�̊��荞�݁i�S��̌��t�̍Č��j
�������̌����i���̔����E�ލ��j �@
�@���̂悤�ɁA���̏�ʂ́A�q�ŋ��r�Ɓq�����̌����r�Ƃ����݂ɓW�J����A�r������q�n�����b�g�̊��荞�݁r�������A�ŋ��́q�ٌ��r�Ɓq�䎌���r�ɂ킯���A����ɑ䎌���́q���܂̐����r�Ɓq���̓ŎE�r�́A������2��\���ɂȂ��Ă���B�Ȃ��䎌����2��\���ɂȂ��Ă��邩�Ƃ����ƁA�䎌���ٌ͖��̏ꊄ�ɏ]���Ă��邩��ł���B���̕\�̂悤�ɁA�ٌ���3��̎ŋ��ƌ��邱�Ƃ��ł��A�䎌���͂�������t�ɂ���Ă���ɋ�̉��������̂ł���B
| �ŋ��̌`�� |
�ٌ� |
�䎌�� |
| �ŋ��̓��e |
1��\���܂̐���
2��\���̓ŎE
3��\�ŎE�҂̋����Ɖ��܂̎���
�Ƃ���3��̖����� |
1�� |
2�� |
�ٌ�1��
�i���܂̐����j�̌��t�ɂ���̉� |
�ٌ�2��
�i���̓ŎE�j�̌��t�ɂ���̉� |
| �����l���̔��� |
�����̊ϋq�́A�I�t�B�[���A�Ɠ����ŁA�ŋ��̂��炷�����Ǝv�����A�����ʼn������邱�Ƃɂ���ďW���ł��A�ŋ��̑S�e��N���ɋL�����邱�Ƃ��ł���B |
��́A�u���̂��܂̐����͂��ǂ�����悤�ˁv�Ƃ����悤�ɁA���Ԃ�̂��Ƃ����Ă����Ă���Ǝv���B |
�f���́A�ŎE��ʂ��ςĐȂ𗧂��đލ�����B |
�@�����炱�ٌ̖��̏ꊄ�ɏ]���Ȃ�A�{���͑䎌����3��i�ŎE�҂̋����Ɖ��܂̎���j�܂ŏ㉉�����͂��ł��邪�A�����ލ����A�|���[�j�A�X���ŋ����~�߂����߂ɏ㉉����Ȃ������̂ł���B
�@����ł͇@�̓䂩�猩�Ă݂悤�B
�@�@�Ȃ������悤�ȓ��e�̌����A�q�ٌ��r�Ɓq�䎌���r�Ƃ��āA��x���J��Ԃ����̂��H
�@
�@
�@����́A�q�ٌ��r�Ɓq�䎌���r�̕\�������̂������ɂ���Ƃ�����B�����܂ł��Ȃ��q�ٌ��r�́A�g�U�肾���̌������A�q�䎌���r�̂悤�Ɍ��t�ňӖ��m�ɓ`���邱�Ƃ��ł��Ȃ������ɁA�u�܂݁v���������邱�Ƃ��ł���B�����ē�����ȗ����ł��邩��A�q�䎌���r���͂邩�Ɂu�Z���ԁv�ŋ������܂Ō����邱�Ƃ��ł���B�n�����b�g�͂��̓����𗘗p�����̂��B�Ȃ��Ȃ�A���͎ŋ����C�ɓ���Ȃ��ꍇ�A���ł��Ȃ𗧂��Ďŋ��𒆎~�����邱�Ƃ��ł���B�����Ȃ茀�̈Ӗ������m�ɂȂ�䎌�����㉉�����̂ł́A���ɒ��~�ɂ����댯�����邩�炾�B�����Ďl�ʑ^�̂̃n�����b�g�ɂƂ��āA���ɓŎE��ʂ�������O�ɁA�����̊ϋq�i�܂艤�̐b���j�Ɏŋ��̑S�e�i���܂̐����A���̓ŎE�A�ŎE�҂̋����Ɖ��܂̎���j�������A�u���͓ŎւɊ��܂�Ď��̂ł͂Ȃ��A���ɓŎE���ꂽ�v���Ƃ�z���`���Ă��炢�����������炾�B����ɂ͒Z���Ԃŏ㉉�ł���ٌ����œK�������̂ł���B
�@
�@�ŋ��̑O�ɉ�������ٌ��́A�G���U�x�X���ɂ�����ŋ��㉉�̍ۂ̊��s�ŁA�V�F�C�N�X�s�A�̎���ɂ͂��łɌÕ��ȕ\���`���ɂȂ��Ă������A�V�F�C�N�X�s�A�͂�����A�ŋ��̑S�e��Z���Ԃ̊ԂɑN���ɉf���o���q����܂�̌��r�Ƃ��ė��p�����B�����炱�̏�ʂٌ̖��́A�G���U�x�X�������̒ʗ�ٌ̖��Ƃ͂������āA�䎌���Ƃ܂������������e�ƋƂ���̓I�ɕ\������Ă���̂ł���B����Ėٌ��̓J�b�g���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂��B
�@
�@���ɇA�́q��r�͂ǂ����H
�@
�A�@�Ȃ����́A�ٌ��̓ŎE��ʂŔ������Ȃ��̂��H �@ �@
�@�q�ٌ��r�ł̉��̔����ɂ��ăV�F�C�N�X�s�A�͂Ȃɂ������Ȃ��������A����������������A�����肵���肹���ɓŎE��ʂ��ς��̂Ȃ�A�Ȃ�炩�̔����������̂����R�ł��낤�B�������́A�܂����̒i�K�ł͓ŎE��ʂ��������Ă����R�̈�v�Ƃ����l����ꂸ�A����₶�Ԃ�̔ƍ߂��n�����b�g�ɒm���Ă���Ƃ͖��ɂ��v��Ȃ������̂ł���B�����牤�͗]�T�^�X�ŕ��Â����Ƃ��ł������A���Ƃ��S�����ꂽ�Ƃ��Ă��A�n�����b�g��z���C�V���[���C�Â��قǂ̔����ł͂Ȃ������̂ł���B
�@
�@�Ō�ɇB�́q��r�͂ǂ����H
�B�@�Ȃ����́A�䎌���Ŕ�������̂��H �@ �@
�@����́A�䎌���i���j���I����Ă���̃n�����b�g�̐S�̓������A����ǂ��čl���Ă����Ή����ł���B�͂��߂̑䎌���i���j�́A��ɂ��Ă��ŋ��ł�����̂ŁA�n�����b�g�͎ŋ����I���ƁA�^����ɕ�i���܁j�̊��z���B�Ă̒�A��͂��Ԃ�̂��Ƃ����Ă����Ă���Ǝv���̂ŁA���������ǂ�����Ƃ����B�n�����b�g�̗J�T�̌����̂ЂƂɂ́A�ꂪ���Ƃ̐�����j���ăN���[�f�B�A�X�ƌ����������Ƃɂ���̂ŁA�n�����b�g�́u���������Ƃ͎��ł��傤�v�ƕ�ɔ���������B���́A����ȉ��܂��C�Â����āu�؏����͕����Ă���̂��H���������͂Ȃ����낤�ȁH�v�Ƃ����˂�B���̉��̖₢�Ńn�����b�g���S�z�����̂́A�ŋ��̒��~�ł���B�����Ŏŋ����I����ꂽ��A���Ɋ̐S�̓ŎE��ʂ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B����ł͌����q���Ȃ�����A�n�����b�g�͎ŋ������s�ł���悤�ɁA���l�̂ӂ�����āu�������V�сA�ŎE�������v�ƒ������B���͂���Ɂu�O��͂Ȃ�Ƃ����̂��H�v�Ƃ����˂�B�n�����b�g�́u�S���U�S�[�E���v�Ƃ͓����Ȃ��B�u�˂��ݎ��v�Ƃ�����g���g���A�E�B�[���ŋN�����E�l�������ŋ��ɂ������̂��Ƃ����B�����փ��V�A�[�i�X���o�ꂷ��B�n�����b�g�̓��V�A�[�i�X���u���̉��v�ƏЉ��B�ӂ��ɍl����A�����̉����E�����V�A�[�i�X�̓N���[�f�B�A�X�̂��Ƃ�����A�u���̒�v�Ƃ����̂����R�Ȃ̂ɁA�n�����b�g�́u���̉��v�ƌ����B�Ȃ����낤�H����́u�ŎE�������v����h�����Ă������̂ŁA�n�����b�g�����l���Ȃ���A���Ԃ�̊�]�����������t���Ɨ�����������B�i���\�Q�Ɓj
|
���̎����
���V�A�[�i�X�̏Љ�Ǝŋ��̍Ñ�
|
�{��������ׂ����t |
���ۂɌ��������t�i�n�����b�g�̊�]�j
|
|
���������͂Ȃ����낤�ȁH
|
����܂�
|
�u�ŎE�������v
|
| �O��͂Ȃ�ƌ����̂��H |
�S���U�S�[�E��
|
�������ł͂Ȃ��u�˂��ݎ��v |
|
���V�A�[�i�X�̏Љ�
|
���̒�ł�
|
�u�˂��ݎ��v�����߂�̂̓n�����b�g
|
| ���������Ԃ��������ߖʂ͂�߂āA�n�߂� |
���� |
�u���̉��v�́u���Q����Ƌ��т���v
|
�@�\���݂�ƁA���͎ŋ��̓��e�ɂ��Ď��₵�Ă���̂ɁA�n�����b�g�͖{�������ׂ����Ƃ�����Ȃ��ŁA���Ԃ�̊�]�������Ă���B�܂�킽�������ɂ̓n�����b�g�����t�V�т����Ă���悤�Ɍ����邪�A�Y�o���{���������Ă���̂ł���B�C�M���X�̊w�҃i�C�W�F���E�A���O�U���_�[�������悤�ɁA�n�����b�g�͂�������A�f���i�N���[�f�B�A�X�j���E�����Ԃ�ƌ����̃��V�A�[�i�X�Ƃ���̉������Ă����B�����ɂ͉ߋ��ɍs��ꂽ���E���Ɩ����ɍs����͂��̉��E�����������Ă���̂ł���B�@
�@�Â��ăI�t�B�[���A���u����̂悤�ɂ悭�������ł��ˁv�Ɛ}���������̂�����A�n�����b�g�͂��ɕԂ��āA�ŋ��Ƃ͂܂������W�Ȃ������Șb�����āA�Ȃ�Ƃ����̏���ʂ���B�n�����b�g�ɂ͗P�\���Ȃ��B�����ŎE��ʂ����Ɍ����āA����̔��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̃n�����b�g�̂�����S���A�u�������Ƃ��A�l�E���B���������Ԃ��������ߖʂ͂�߂āA�n�߂�v�Ƃ����䎌�ɂȂ��Č����B�����Ă����ł܂��A���Ԃ�̊�]�������B�u���킪�ꐺ�̑�K���X�A���Q����Ƌ��т���v�B�n�����b�g�͂��͂�u���o�ƌ��ϋq�v�ł͂Ȃ��B���҂��̂��̂ł���A����Ƃ������E�����z���Ă��܂��Ă���B
�@
�@���V�A�[�i�X�������J���B�u���͂����肵�ғłŁA���₩�Ȃ閽�A�������ɒD���v�B���V�A�[�i�X�͌����̖��鉤�̎��ɓŖ���������B���̏�i�����ł̓n�����b�g�ɂ͕s�����B�����Ŗ��҃n�����b�g�͌������Ԃ���B�u�뉀�ʼn���ŎE���A���ʂ�D���̂ł��B���̖��O�̓S���U�S�[�B���̘b�͍����c���Ă��āA�I�蔲���̃C�^���A��ŏ�����Ă���B�����A�����������̐l�E���̓S���U�S�[�̔܂������������܂��v�B���́A���̓ŎE�̏�i�����Ȃ���A�Z�E�����ŋ��ɂ���Ă��邾���łȂ��A�n�����b�g�����Q�̂��߂ɂ��̎ŋ�����������ƂɋC�Â��B���̎��ɂ̓n�����b�g�̌�肪���X�ɔ�э���ł���B�ڂ̑O�ł͂��ԂƂ����Z�E�����Č�����Ă���B���́A���̎��o�ƒ��o�̗�������̍U���ɂ���āA�ۉ��Ȃ��ɌZ�E���̎��i���v�������ׂ�B�ウ�ꂵ��Ŏ��ʌZ�B���̎肪�k�������B���̓ł𒍂����肪���B�k�����́A�~�߂悤�Ƃ��Ă��~�߂��Ȃ��B�u�����A�Z�̎��[���痧������Ȃ���v�B���͎E�Q�̌��ꂩ�瓦���B�I�t�B�[���A���^����ɋC�Â��B�����ĉ��܂��v�̗l�q��s�R����B���́A�u����������āB���ցv�Ƃ����ċ���B
�@���̂悤�ɉ����䎌���i���j�̓r���őލ������̂́A���V�A�[�i�X�ƌ���ł�����҃n�����b�g�̔��^�̉��Z�ɂ���āA�Z�E���̎��i���v�������сA�����̉����Z�Ǝ��Ⴆ�A�ꍏ�������Z�̎��[���瓦�ꂽ����������ł���B�����l���Ȃ���A�n�����b�g���ŋ����v�����Ƃ��ɂ����u�߂�Ƃ����҂��ŋ������Ă��邤���ɁA�^�ɔ���������ɍ����䂳�Ԃ��A���̏�Ŕƍs�����������v�Ƃ͂Ȃ���Ȃ����A���Ƃ��Đ������Ȃ��̂��B
�n�����b�g�@���҂Ƃ͖��d�s�v�c�Ȃ��̂��B�������G���炲�ƂȂ̂ɁA���肻�߂̏�M�ɑł����݁A�S�g�S������̂�̑z���͂̓����ɂ䂾�˂�B���̂�������ʂ͑����ƂȂ�A�ڂɂ͗܂��ׁA�\��͋��������A���͂�����A�ꋓ�ꓮ���S�ɕ`���l�����܂��܂��Ɖf���o���B�Ȃ�̂��߂��H�w�L���o�̂��߁I�w�L���o�͂��̒j�ɂƂ��ĉ����H���̒j�̓w�L���o�ɂƂ��ĉ����H����Ȃɋ������肵�āB���������̒j�ɉ��Ɠ������@������A�{����o�������������o����A��̂ǂ����邾�낤�B�����܂łЂ��������܂����䎌�Ŋϋq�̎����������낤�B�߂���҂̋C�����킹�A�߂Ȃ��҂����̂̂����A�����m��Ȃ��҂��R�Ƃ����A�ڂƎ����^�킹�邾�낤�B
�@���҂̉��Z�Ɋ��������n�����b�g�ɂƂ��āA���҂Ɲh�R�ł���̂́A�݂����炪���҂ɂȂ��ĉ����邱�Ƃ������B�Ă̒�A���͖ڂƎ����^���A�u�C�����킹�v�đގU�����̂��B
�@���̂悤�ɁA�V�F�C�N�X�s�A�����̏�ňӐ}�����̂́A�ŋ��͍ߐl�̈������S���������邱�Ƃ��ł�����̂����A����͂Ȃɂ������҂̉��Z�ɂ���Đ�����������
�Ƃ������Ƃł���A�����ŏd�v�Ȃ̂͂�����̂̎ŋ�����N���[�f�B�A�X���Z�E���̎��i���v�������ׂ�悤�ɁA���\�̐��E�������̐��E�𗽉킷�邱�Ƃ��V�F�C�N�X�s�A�����ڂ����Ƃ������Ƃł���B
|
|
|
|
|
|
|
|





